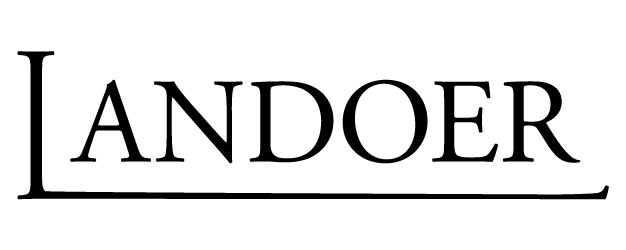映画『CLOSE/クロース』
脆さから生まれる〈強さ〉
胸を張って自分の声に耳を澄ませて
毎分毎秒、空の表情が変わるように、私たちがもつ〈正しさ〉や〈大切〉も変わり続けている。でも、それに気づくのはずっとずっと大人になってからで、それを受け入れることができるのは、さらにそのずっと後だったりする――『CLOSE/クロース』は、そういった子ども時代の自分の揺らぎが、画面越しに胸を刺す作品だ。自分にすら分からない、自分の〈未知〉を「何がなるか分からない“庭”」と表現した監督。自分という庭に顔を出す、花や実を待つのが人生ならば、どうかその種から愛してほしい。いついかなるときも、どんな嵐がこようとも、あなたは、あなたのまま、あなたの声を聴けばいい。あなたの庭に芽吹くものを描けばいい。そんな作品と表現のお話を、海を越えてお届けにまいりました。
映画『CLOSE/クロース』

-Story-
花き農家の息子のレオと幼馴染のレミ。昼は花畑や田園を走り回り、夜は寄り添って寝そべる。24時間365日ともに時間を過ごしてきた2人は親友以上で兄弟のような関係だった。13歳になる2人は同じ中学校に入学する。入学初日、ぴったりとくっついて座る2人をみたクラスメイトは「付き合ってるの?」と質問を投げかける。「親友だから当然だ」とむきになるレオ。その後もいじられるレオは、徐々にレミから距離を置くようになる。ある朝、レミを避けるように一人で登校するレオ。毎日一緒に登下校をしていたにも関わらず、自分を置いて先に登校したことに傷つくレミ。二人はその場で大喧嘩に。その後、レミを気にかけるレオだったが、仲直りすることができず時間だけが過ぎていったある日、課外授業にレミの姿はなかった。心ここにあらずのレオは、授業の終わりに衝撃的な事実を告げられる。それは、レミとの突然の別れだった。移ろいゆく季節のなか、自責の念にかられるレオは、誰にも打ち明けられない想いを抱えていた…。

映画『CLOSE/クロース』
×
ルーカス・ドン監督
『CLOSE/クロース』は、自分が登場人物たちくらいの歳のときに経験した、誰にも話してこなかったことを解放した作品です。登場人物たちと同年齢の頃、作品に描いていることについて、なかなか話すことができず、レオと同様「近くにいたい」と思っていた友人を自分から押しやってしまったことがあったんです。当時の僕は「集団に属していたい」という気持ちが強かったんだと思います。過去においてきた傷と対峙する、そこにはすごく大きな力があると思い、今回この作品の制作を決めました。もちろん人によっては、傷が大きすぎて「傷から良いものが育つなんて不可能だ」と思うこともあるかもしれないのですが…。ただ、それでもやっぱり、この映画を観ていただいた皆さんから「“自分”という人間が存在していることを見てもらえた気がする」だとか、「自分が自分の過去を訪れるキッカケになりました」などの言葉をいただく機会が多くて。そういった声をお聞きして、脆いものから強いものが芽を出すのかな、と思いましたし、「この映画の最後に語られることは〈強さ〉なんだろう」と、改めて気づくことができました。
大人になった監督が、
いまを生きる子どもたちに
伝えたいことはありますか?
今回、撮影現場でたくさんの子どもたちに囲まれていて、僕が教わることが多かったです。僕が子どもの頃よりも「自由な表現をしていいんだ!」と感じている若い子がとても多いように感じました。社会がジェンダーについて構築してきた狭いスペースから、彼らは遠ざかっていっているように感じて、ものすごく〈希望〉を感じましたね。


実際に子どもたちと関わって
感じられた〈未来〉ですね。
そうですね。昔からある弱肉強食のような「一番大きな声をあげた人がリーダー!」といった空気感ももちろんあるのですが、なにか柔らかかったり、優しかったりする場所から〈強さ〉は育つのだと、子どもたちを見ていて感じました。僕自身が子どもたちから教えてもらったことを体現できる自分でありたいと思いますし、もし子どもたちに声をかけるのであれば、「自分に対して親切であってほしい」と声をかけると思います。少しずつ世界のことを学んでいく途中で、自分の道のりを形作っていくことって、とても〈勇気〉のいることだと思うんです。でもその〈勇気〉を出すことで得られるものってとても多くて…と言いつつ、僕はレクチャーする人ではないので『CLOSE/クロース』が教育的にとらえられてしまったらどうしよう…(笑)。
『CLOSE/クロース』を拝見して、
私は“教育的”というよりも、
過去の自分に手を差し伸べにいった感覚でした。
良かったです。僕が映画作りが大好きなのは、レッスンをしなくてもいいからなんです。映画を通して誰かに何かを教えたり、モラルがどうだと述べたりすることにまったく興味がなくて。単に“人間”の姿を皆さんに見せたいんですよね。例えば『CLOSE/クロース』だったら、社会が押し付ける規範や、ラベル、そういったものから純化されてゆく人々の姿を感じてもらって、そこで各々に芽生えたものを感じてもらえたら嬉しいな、と思います。

ご自身の経験や、シェアしたいものを
大好きな“映画”で表現されている監督。
自分の〈好き〉から表現を生み出したい
と思っている方々に
メッセージをいただけますか?
僕の作った作品は〈怒り〉という感情に根差していたり、〈怒り〉が生まれてきたりする作品が多いのですが、不思議なことに、自分のなかに〈怒り〉を溜めているということは一切なくて。ただ、私たちは人生を生きてゆくなかで、本当に幅広い感情を感じていて、例えば、〈葛藤〉から美しいものや素晴らしいものが生まれてくることがあるように、感情からいろいろなものが生成されていくと思うんです。ただ、多くの人はその生成を「自分にはできない」と思い込んでしまっているんじゃないかな、と。自分自身を批判して、自分が生み出せるものをブロックしてしまっている方が多いように感じます。本来であれば、自分のなかに自然と芽生えたものを成長させていけばいいのですが…。願うことは、皆さんのなかに生まれる思考やアイデア、クリエイティビティなものに対して、自分がいちばん寛容であってほしいということですね。
それぞれがオンリーワンだからこそ
「自分にはできない」ではなく、
“自分にしかできない表現”があるはずですもんね。
そうなんです。去年の10月にセリーヌ・シアマ監督へ質問をさせていただける機会があって、その時に「若いエネルギッシュなクリエイターたちに、どんな声をかけますか?」とお伺いしたんです。その答えが、僕の中ではすごく意外であり、腑に落ちるようなもので。監督は「自分のなかにすごく簡単に、楽にくるものを表現しなさい」とおっしゃったんですよ。作品を作るときって、「苦労して、大変なことを乗り越えてテーマを見つけている」と思われることが多いのですが、監督は「自分が言いたいこと、自分が表現したいこと、それを〈許容〉さえすれば、テーマはパッと出てくるんじゃないか」と。「確かにな」と、僕の映画作りとの共通点を感じました。「こうしたら良いものになって成功する」と、自分のなかにあるはずのものを一生懸命探すのではなく、自分の核にごく自然に存在しているものを育てていけばいいんだと思います。そういった意味で、僕の映画作りは“庭”のようなものなんです。

“庭”ですか!
最後にその心を教えてください。
そうです(笑)。野菜を育てているけれど、何が芽となって出てくるかは分からない。そこで実がなったものを摘んでいくといったもの。ただ、同時に他の野菜たちにも水をあげているから、結果的に自分のクリエイティブな庭を大切にできているといいますか。次はどんな芽が出てきて、どんな実をつけるのか、僕自身、とても楽しみです。

ルーカス・ドン監督
1991年、ベルギー、ヘント生まれ。
柔らかな土壌に愛と涙を注ぎ、
つけた〈実〉から人間味薫る美しい物語を生成するDOER。
【PROFILE】
ヘントにあるKASKスクールオブアーツ卒業。在学中に制作したショートフィルム『CORPSPERDU』(12)が数々の賞に輝き、2014年に製作した『L’INFINI』は2015年度のアカデミー賞短編部門・ノミネート選考対象作品となった。2018年に『Girl/ガール』で長編デビュー。第71回カンヌ国際映画祭カメラドール(新人監督賞)受賞をはじめ、数々の映画賞に輝いた。本作では自身の経験を基に少年たちの友情と悲劇を描き、第75回カンヌ国際映画祭コンペティション部門グランプリ受賞をはじめ、第95回アカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされるなど世界各国の映画賞を席巻した。

映画『CLOSE/クロース』
2023年7月14日(金)ROADSHOW
監督:ルーカス・ドン
脚本:ルーカス・ドン、アンジェロ・タイセンス
キャスト:エデン・ダンブリン、グスタフ・ドゥ・ワエル、エミリー・ドゥケンヌ
Staff Credit
カメラマン:興梠真穂
ヘアメイク:久保マリ子
インタビュー・記事:満斗りょう
ページデザイン:古里さおり