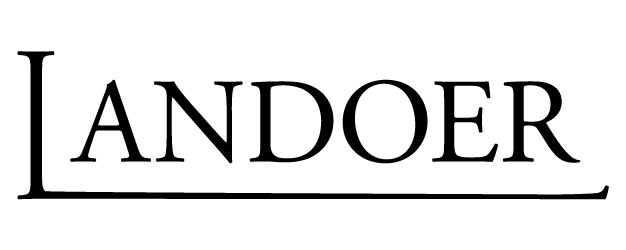映画『宝島』
「想いのバトンは繋がってゆく」
〝宝の島〟で命の炎をたぎらせた
英雄たちのスペシャル対談
大切な人の消息は、それまで刻々と刻んでいたはずの人生の時間を止めてしまう。生きていかなければ、いつまでもここにはいられない、そう思えば思うほど〝あなた〟を忘れてしまうのではないかと、〝あなた〟から離れてしまうのではないかと、大きな不安とわずかな罪悪感が心を覆う。それでもやっぱり、私たちの鼓動は脈を打つ。心は動き、身体は歳を重ねる。だからもう生き尽くすしかない。〝あなた〟と出逢って、私の中に芽生えた変化や異彩の輝きは、例え光源をなくしてもここで灯り続ける「共在」の篝火。〝あなた〟――そう呼びかけたい、あの日を生きた先人たち。〝あなた〟が灯した命の炎を、今度は私たちがたぎらせてみせる。さぁ目を覚ませ、夜明けがやって来る。
映画『宝島』

-Introduction-
ある夜、一人の英雄が消えた。
アメリカ統治下の沖縄で、自由を求め駆け抜けた若者たちの
友情と葛藤を描く感動超大作。
戦後沖縄を舞台に、史実に記されてこなかった真実を描き切った真藤順丈による傑作小説『宝島』。審査委員から満場一致で選ばれた第160回直木賞をはじめ、第9回山田風太郎賞、第5回沖縄書店大賞を受賞し栄えある三冠に輝いた本作を実写映画化。監督を務めるのは、時代劇からアクション、SF、ドラマ、ミステリーやファンタジーまで、常に新たな挑戦をし続ける大友啓史(NHK大河ドラマ「龍馬伝」、『るろうに剣心』シリーズ、『レジェンド&バタフライ』)。主演には妻夫木聡を迎え、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太ら日本映画界を牽引する豪華俳優陣が集結。日本に見捨てられ、アメリカに支配された島、沖縄。全てが失われ、混沌とした時代を全力で駆け抜けた“戦果アギヤー”と呼ばれる若者たちの姿を、圧倒的熱量と壮大なスケールで描く、サスペンス感動超大作が誕生!2019年に企画が動き出してから、6年の歳月を経て遂に公開となる本作。当初開発は順調に進み2021年にクランクイン予定だったが、度重なるコロナ禍に二度の撮影延期を経て実際にクランクイン出来たのは2024年2月。スタッフ・キャスト全員が「どうしても今の時代に届けたい」という強い情熱を持ち進んできたからこそ実現した奇跡のプロジェクトがついに公開。沖縄戦や、本土復帰後を描いた沖縄に関連する映画は過去にも多く製作されてきたが、本作は名匠・大友監督のもと<沖縄がアメリカだった時代>を真正面から描き切るかつてない“本気作”。実際に起きた事件を背景に進行する物語に、当時の状況を徹底的に調べ尽くし、リアルな沖縄を再現。クライマックスのシーンでは、延べ2,000人を超えるエキストラが投入され、その群衆一人一人にまで演出を加えていく大友監督により、当時の息遣いまで再現されたリアルな感情の爆発シーンなど、想像を遥かに超えたインパクトで描かれる。東映とソニー・ピクチャーズによる共同配給のもと、ハリウッドに拠点を置くLUKA Productions Internationalも製作に参加して日米共同製作で挑む、今までの常識を覆す、革新的なエンターテイメント超大作。
-Story-
英雄はなぜ消えたのか?
幼馴染3人が20年後にたどり着いた真実とはー。
1952年、沖縄がアメリカだった時代。米軍基地から奪った物資を住民らに分け与える“戦果アギヤー”と呼ばれる若者たちがいた。いつか「でっかい戦果」を上げることを夢見る幼馴染のグスク(妻夫木聡)、ヤマコ(広瀬すず)、レイ(窪田正孝)の3人。そして、彼らの英雄的存在であり、リーダーとしてみんなを引っ張っていたのが、一番年上のオン(永山瑛太)だった。全てを懸けて臨んだある襲撃の夜、オンは“予定外の戦果”を手に入れ、突然消息を絶つ…。残された3人は、「オンが目指した本物の英雄」を心に秘め、やがてグスクは刑事に、ヤマコは教師に、そしてレイはヤクザになり、オンの影を追いながらそれぞれの道を歩み始める。しかし、アメリカに支配され、本土からも見捨てられた環境では何も思い通りにならない現実に、やり場のない怒りを募らせ、ある事件をきっかけに抑えていた感情が爆発する。やがて、オンが基地から持ち出した“何か”を追い、米軍も動き出す――。消えた英雄が手にした“予定外の戦果”とは何だったのか?そして、20年の歳月を経て明かされる衝撃の真実とは――。
グスク役 妻夫木聡
×
レイ役 窪田正孝

原作がもつ圧倒的な熱量を胸に、
先人たちと向き合い続けた日々
LANDOER:脚本を読んで、ご自身の役柄にどうアプローチをしていこうと考えられましたか?
妻夫木聡(以下、妻夫木):最初は役柄よりも、原作のもつ圧倒的な熱量をどこまで脚本を通して役に落とし込めるかが課題だと感じました。あとはそもそも、映画化できるのかといったところも。撮影をするにあたって、基地などのロケ地の確保はできるのか、とにかくお金がかかるんじゃないか、そういったことが最初に頭に浮かんでしまいましたね。
LANDOER:読んで役を築く、それより以前に課題や長い道のりがあったんですね。
妻夫木:そうですね。まずは“沖縄と改めて向き合うこと”が、自分の一番の課題にあがりました。ただ演じることに集中していればいいといった次元ではなかったので、沖縄の歴史を学ぶところからはじめて。当時を生きた方々にインタビューをさせていただいたり、資料館を巡ったりしながら本当に多くのことを学ばせていただきました。そのなかで、親友が導いてくれた佐喜眞美術館に展示されていた『沖縄戦の図』(丸木位里・丸木俊)という画が、僕の〈核〉になってくれたんです。【戦争】というものが詰め込まれたその画を見たときに、あの日の彼らの〈声〉が自分の中に入ってきて動けなくなってしまって。まるで「どこか分かった気になっているんじゃないか」と、そう言われているような気がしたんですよね。その瞬間、自分は“感じる”ということを忘れていたんじゃないかと気づかされました。

窪田正孝(以下、窪田):僕はお話をいただいて、妻夫木さんとまたご一緒できること、しかも深い関係性のある役柄での共演だということ、そして大友(大友啓史)監督や他のキャスト、スタッフの方々と作品づくりができるということにとても心惹かれた、というのが最初の印象です。そこから脚本を読ませていただいたのですが、現代の感覚ではどうしてもうまく読み込めず、役のことがまったく理解できなかったんです。当時は携帯電話などがないアナログな環境で、隣人との間にプライベートも存在しないような世界。そうした「みんなが家族!」という感覚を落とし込んだうえで脚本を読んで初めて、いろいろなものが紐解いて見えてきました。
LANDOER:紐解いた先で、窪田さんが脚本にもった印象や感想はどういったものでしたか?
窪田:今の時代にこそ描かなければならない日本、そして日本人が向き合わなければいけない物語だと思いました。もしあの日、日本が戦争に勝っていたとしたら、日本はもっと豊かになっていたと思うんです。沖縄をはじめ、日本にはいたるところに敗戦の爪痕が残っている。そしてそれは現在の政治なんかにも表れているような気がしていて。この作品を通して、僕たち日本人は絶対に変えられない事実に目を向け、今一度ここで立ち止まって考えるべきなんじゃないかと思わされました。役者として、この作品に携わらせていただけてものすごく光栄ですし、“演じる意味”をもたせていただけたことも、僕の中でとても大きかったです。

「お互いが、お互いの人生を生きてきた」
芝居の交流地点で光る、圧倒的信頼
LANDOER:いたるところで激しい感情のぶつかり合いが繰り広げられる本作ですが、お二人の間で芝居の打ち合わせなどはされましたか?
妻夫木:いや、キャスト同士では何も話していないよね?
窪田:ないですね。
妻夫木:もともと窪田くんとは仲が良かったのですが、本格的に一緒に芝居をするのは今回が初めてで。お互いがお互いを知っているからこそ、話さなくても通じる気がしてあまり話し合いにならなかった…というより、そもそも「話し合おう」と考えてすらいなかったですね。窪田くんは窪田くんが思う“レイとしての正義”に向き合って生きてくる、僕は僕で“グスクとしての正義”とずっと向き合って生きている。最終的にはお互いの感情がぶつかり合うことになるのだけれど、そこの局面に向かって「お互いがお互いの(役の)人生を生きてきた」という自負と信頼があったので、なおさら話しませんでした。あとは、キャストや監督だけでなく、この作品に携わっているスタッフの皆さんそれぞれが想いをもって臨まれていたので、美術さんやメイクさん、衣裳さんなどの、“技術をもって『宝島』の時代にタイムスリップさせてくれる力”を信じていました。撮影中、現場に入ると自然とグスクになれる環境に助けられていましたね。

LANDOER:「話し合う」ということ自体が、その場では不自然だったんですね。
妻夫木:話し合ってうまくいくんだったら、話し合ったほうがいいのかもしれないけれど、僕たちは現代の人たちにはないもの、言葉として存在しないものを表現して届かせようとしていたので、現場で細かな演出をつけるというよりは、「それぞれが抱えている想いを、この場でぶつけ合おう」といった空気が流れていた気がします。
LANDOER:大友監督は芝居を役者の方々に委ねられる、という話をお聞きしたことがあるのですが、窪田さんは大友監督の現場の空気をどう感じていらっしゃいましたか?
窪田:監督はセリフを求めているわけでなく、言葉ではない何かを映し出そうとされているんだな、というのは感じていました。常に、“あの時代の沖縄に丸裸の状態で投げ出された人間の内側からは何が出てくるのか”にフォーカスを当てていらしたので、それが出てくるまで「OK」がかからないんです。僕たちは丸裸の状態で、内側から湧き出てくる感情を体現し続けていた記憶があります。セリフの言い方を変えただとか、沖縄弁がうまく話せただとか、そういった表面的なことができるのは当たり前。それよりも、例えば食べるものがなかったとしたら、グスクやレイはどういった行動を起こすのか、どんな顔をするのかを監督は大切にされていて。そのうえで僕ら役者は、監督の想像を超えて自分の感情をどう映し出すのか、そういった芝居を試されては提示して、を繰り返す毎日でした。

2000もの命の炎が渦巻いた、
“コザ暴動”シーン撮影の裏側
LANDOER:2,000人のエキストラが参加したコザ暴動シーンの撮影はいかがでしたか?
妻夫木:もともとコザ暴動のシーンは、千葉にオープンセットを組んで大々的に撮影する予定だったのが、沖縄で撮影をしている最中に東京のスタジオで行うことが決まったんです。正直、オープンセットからスタジオに規模が縮小されたように感じて不安もあったのですが、そこで監督のすごさを改めて垣間見ました。監督は「“人”こそ最大の飾り」とおっしゃっていて、コザ暴動のシーンの撮影でも、その言葉を具現化するようにエキストラの方一人ひとりに演出をつけられていたんです。それって、普通の撮影だったらありえないことなんですよ。チーフクラスの助監督さん3、4人がそれぞれのエキストラメンバーに芝居をつけて、なかでも沖縄出身の俳優さんたちには、ところどころで率先して芝居をしてもらうように伝えていて。そうしてみんなでどんどん鼓舞し合っているうちに、エキストラさん一人ずつに命の炎が灯っていくのが見えたんです。あの瞬間、僕の目には実際のコザ暴動が動き出す気配が映った気がします。それは生命力の塊であり、「俺たちはここで生きているんだ!」という魂の叫びでもあったなと。僕は皆さんのお芝居から、そういった命の叫びを学ばせていただきました。
LANDOER:2,000人の命の炎が灯ってゆく瞬間…。たしかにあの場面には魂の叫びと命の炎が映っていました。ちなみに、エキストラの皆さんにはどういった演出がなされていたのでしょうか?
妻夫木:ちらっと聞いた話では、とにかくコザ暴動が起きた時代背景や内容の説明を伝えていたみたいです。コザ暴動は“暴動”と呼ばれているけれど、死者が一人も出ておらず、朝7時半には自然解散になっているんです。でもそこに集った方々には、それまで虐げられてきた時間が確実に存在していて、いろいろな思いもあったはず。監督はそれらを踏まえて、「一人ひとりにストーリーがあります」ということを熱心にお話しされていましたね。そんな監督の言葉を受けて、うちなんちゅの俳優さんたちにも火がついたのか、芝居についての話し合いがはじまって。そして今度はそれを見た助監督さんたちが「あなたはもっと傍観者としていてほしい」などと、一人ずつに芝居をつけはじめたんです。僕らも誠心誠意ぶつかっていかなければという気持ちで、一緒に芝居をさせていただきました。

LANDOER:妻夫木さんが笑みを浮かべるような表情で、数多の感情が入り乱れる渦中を歩いている姿が印象的でした。
妻夫木:僕としては、僕のことは気にせずにエキストラの皆さんには芝居を続けてほしかったのですが、本当に日本の方ってやさしくて、僕が歩こうとすると皆さん避けてくれちゃうんですよ(笑)。でも、実際のコザ暴動中にはそんなことがあるはずないので、「全然気にせずに来てくださいね」とお声がけをして、皆さんの芝居に僕のことをたくさん利用してもらうようにしていました。
LANDOER:窪田さんはご覧になってみていかがでしたか?
窪田:“コザ暴動”は、歴史的に見てもとても大きな出来事であり、本作でも一番フォーカスされていた部分。僕は想像でしか話せないけれど、あのシーンを観て「きっと本来の人間ってこうなんだろうな」と思いました。人間ってその場に順応していく生き物なので、当時の沖縄の状況を考えると、もどかしいことや悔しいことがあっても、それらが当たり前すぎて何も言えなかったと思うんです。もちろんめちゃくちゃ怒りを感じることだってあったはずで。コザ暴動は、そういった溜まりに溜まった気持ちが“沖縄の魂”として一つの方向を向いた結果、必然的に起きた暴動だったんじゃないかな、と。あのシーンには、そういった一人ひとりの声が非常にリアルに描かれていると思いました。

自分なりの〈正義〉で愛を貫いた
孤独な男の英雄譚
LANDOER:当時の歴史や若者たちの姿に触れたことで、レイという役柄への解像度が上がった部分があれば教えてください。
窪田:当時の方たちのことを分かりきることはできないけれど、少なくともこれだけ言葉が溢れていて、顔を合わせなくても簡単に言葉を届けられる現代とはまったく違う〈正義〉が存在していたんだろうと思いました。もし今、あの頃と同じように携帯電話がなくなったとしたら、人間はアナログなことしかできないわけじゃないですか。しかも敗戦国としてアメリカに占領されている世界では、自分たちの声はまったく届かないし、いくら訴えても何も変わることがないわけで。そういった状況下で、レイに残されたものは暴力しかなかったんじゃないかと思うんです。暴力という武器を使って兄を探す——レイにとっては兄を失ったことが、超えるべき新たな課題になっていたんだと思います。もしあのまま兄がいたとしたら、ずっと「オンの弟」として兄の背中を追って、兄のつくった道を生きていた。それが兄を失ったことによって、一人の人間として自分で選択をし、意思をもって行動しなければならなくなった。僕は、悲しみの中で自分なりに兄を探すことが、いつの間にか“レイの正義”へと変わっていったんじゃないかと考えていました。
LANDOER:『宝島』の登場人物たちは、それぞれの〈正義〉を色濃くもっていますが、レイの〈正義〉には「こうするしかない」という苦しさが垣間見える部分も多かったです。
窪田:あの時代、言葉で言っても通じない場合、男性に残された手段はおそらく武力行使しかなかったと思うんです。レイは、警察や政界などの表面的につくられた世界から兄を探すのではなく、よりリアルに、そしてシンプルに世の中を見渡すことのできる裏の闇の世界から探そうとした。そこには彼なりの強い〈正義〉を感じます。兄への愛情がなかったら、あそこまでの行動はできなかったと思いますし。だからこそ僕がレイを演じるならば、レイの一番の味方でいなければならない、彼が人から非難されるような行動をしたとしても自分だけは味方でいようと思いながら演じていました。

膠着状態が続いた作品づくり
そこで見出したのは、“必然”の可能性たち
LANDOER:本作はクランクインまでに二度の延期を受けたとお聞きしました。そんななかでもこの作品を世に出したいと保ち続けられたモチベーションは何でしたか?
妻夫木:今言えることは結果論でしかないのですが、正直もう、信じるしかないと思っていました。窪田くんとも『ある男』(2022年、石川慶監督)で共演して以来、「また一緒にやれるかもね」という話をしていながら延期、延期の連続だったので。とはいえ僕は、起きたことには意味があると思っているんです。結局今年の公開になったけれど、期せずして今年は戦後80年の年。しかも延期になる度に、撮影期間も役者のスケジュールも増えていったんです。そう考えると、今までの延期は「お前らもっとやれることがあるんじゃないか」と神様がくれた時間であり、必要な試練だったんじゃないかと思いはじめて。すべては導かれた結果、今こうなっているのかなと思います。まぁ、出来上がった今だから言えることなんですけど…(笑)。やっぱりそれだけの月日を待ってクランクインを迎えたときは、「撮影している…!」という喜びと嬉しさがありましたね。
窪田:本当に膠着状態が長く続いた作品で、その間、自分たちはただ待つことしかできなかったですし、一度話がなくなっていた手前、またなくなるかもしれないという覚悟もしていました。正直「この期間、撮影がなくなったらオフになるな~」なんて考えていた時期もあったのですが、いざ動き出すことが決まったときに「やっぱり自分はこの作品をやりたかったんだ!」という気持ちに改めて気づくことができて。そこから撮影で沖縄へ行くことになり、最初は「ラッキー」と思っていたものの、役を通して見た『沖縄』という地が全然気持ちよくなくて、逆にとてもしんどかったことを覚えています。僕、撮影期間中に水着を持って行っていたのですが、沖縄の海に入ることが怖くなってしまって入れなかったんですよ。そのとき初めて、自分でも気づかないうちにレイとの距離がものすごく近くなっていたことを実感しました。「この撮影期間中は一人の人間としてもがき苦しみながら、自分の役割をまっとうするしかない」と。撮影を終えてプライベートで訪れた沖縄は、撮影中と違ってとても気持ちのよい場所でした。

Dear,これからの未来を創るLANDOER読者へ
「例え〈死〉を迎えても、〈想い〉は残される。
そんなふうに命は繋がってゆく」
From 妻夫木聡
シンプルだけれど「今があるって、当たり前じゃない」ということは、ずっと感じていてほしいと思います。過去の歴史を知っている人も知らない人も、僕たちはみんな先人たちの想いを受けて生きていると思うんです。〈死〉は終わりを意味するものだと思っていたけれど、例え〈死〉を迎えても〈想い〉はずっと残ってゆく——それは、〈想い〉の主と一緒に生きていることを意味するのではないかな、と。命ってきっとそういうふうに、どんどん繋がっていくものなのだと僕は思います。作品への入り口はどういったものでもいい。ただ、この映画を観て何も感じない人はいないと思っていますし、そのくらい自信をもっているので、もし少しでも興味が湧いたら観に来てほしいなと思います。鑑賞後、どう感じるかは一人ひとりの心に委ねますが、少なからず未来のカタチを変えていく力を感じていただけるはずです。
「コンテンツに富んだ時代、
これからの日本を担う皆さんに、
この作品が見つかることを願って」
From 窪田正孝
現代は本当に情報やコンテンツに溢れていて、良質なものをつくることよりも、時間のない中でどれだけ量産できるかということが重視されているような気がしています。もちろんバラエティーがたくさんあることは良いことだと思うのですが、僕は、本当に良いものが埋もれてしまうという懸念も感じていて。新しい情報やコンテンツが積み重なっていくのを止めることはできないけれど、『宝島』のような作品はなかなか生まれ出ない作品だと思うので、たくさんの選択肢の中から見つけていただけたらすごく嬉しいです。つくった側の想いを知って欲しいと思うのはこちら側のエゴなので、伝えるのが難しいのですが…。この映画が僕らの想いとともにこれからの日本を担う皆さまに届いて、何か生きていくヒントになってくれたら嬉しいなと思います。


映画『宝島』
全国公開中
出演:妻夫木 聡
広瀬すず 窪田正孝
中村 蒼 瀧内公美 / 尚玄 木幡竜
奥野瑛太 村田秀亮 デリック・ドーバー
ピエール瀧 栄莉弥
塚本晋也 / 永山瑛太
原作:真藤順丈『宝島』(講談社文庫)
監督:大友啓史
配給:東映/ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

Staff Credit
カメラマン:YURIE PEPE
ヘアメイク:勇見勝彦(THYMON Inc.)(妻夫木)/ 菅谷征起(GARA)(窪田)
スタイリスト:片貝俊(辻事務所)(妻夫木)/ 菊池陽之介(窪田)
インタビュー・記事:満斗りょう
ページデザイン:Mo.et