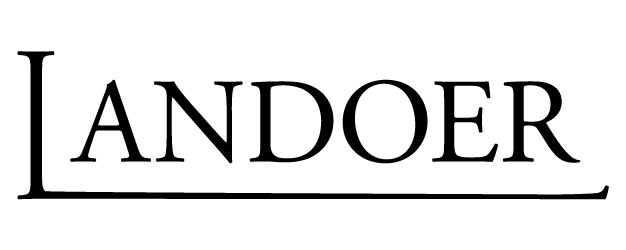「心」と向き合い、
「愛の本質」に触れたい貴方へ

-INTRODUCTION-
民主国家としての土台を築いていた激動の時代である 1991 年のポーランドを舞台に、NY で生まれ育った娘と、約 50 年ぶりに祖国に戻った父が繰り広げる異色のロードムービーが完成した。第 74 回ベルリン国際映画祭でプレミア上映され、各国のメディアらに広く感動の輪を広げたのは、全編を貫くユーモアと前向きなテーマ。全くかみ合わない父と娘が、相手の言動に容赦ない辛口のツッコミを連打し笑いを誘う珍道中かと思いきや、それぞれの心の傷にも鮮やかに光が当てられ、封印してきた過去と向き合うことで、未来へと新たな一歩を踏み出す姿が描かれる。さらに深い共感を呼んだのは、ホロコーストへの今日の問題としてのアプローチ。生存者の娘を主人公に据えて、戦争未体験の世代にも落とす影にフォーカスすることで、今を生きる私たちの物語として胸に迫る作品に仕上げることに成功した。
-STORY-
ニューヨークで生まれ育ったルーシーは、ジャーナリストとして成功しているが、どこか満たされない想いを抱えていた。その心の穴を埋めるため自身のルーツを探そうと、父エデクの故郷ポーランドへと初めて旅立つ。ホロコーストを生き延び、その後決して祖国へ戻ろうとしなかった父も一緒だ。ところが、同行したエデクは娘の計画を妨害して自由気ままに振る舞い、ルーシーは爆発寸前。かつて家族が住んでいた家を訪ねても、父と娘の気持ちはすれ違うばかり。互いを理解できないままアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所を訪れた時、父の口から初めて、そこであった辛く痛ましい家族の記憶が語られるが──
伊藤さとり’s voice
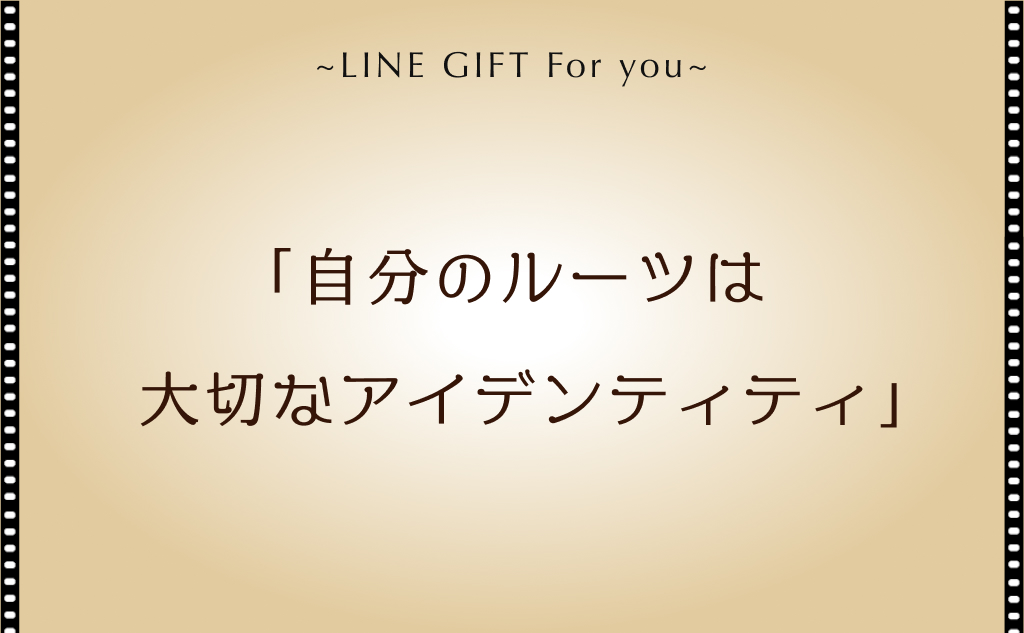
主人公のルーシーは魅力的な人物かと問われたら、そうとは言い切れない自分がいる。それなのにこの親子の旅から目が離せず、二人の関係がどうなっていくのか気になって仕方がなかった。きっとその理由はどこにでも居る飾らない親子の姿だからで、自分と親との関係にほんの少しだけ似ている気がするからかもしれない。それだけ他人事に思えない映画であり、自分のルーツにも気付かされる物語だった。
NY出身のルーシーと父親は体型こそ似ているものの、性格は大違い。社交的な父親は誰とでも会話をするが、ルーシーはあまり心を開かない。ただこの映画の舞台が父親の故郷ポーランドでの親子二人旅なので、父親はポーランド語が話せるのに娘は英語しか話せないということもあるのかもしれない。ただルーシーは、フリーマーケットで日用品を売っている貧困に苦しむ女性の願いに応えて要らないものを購入してしまう時点で、非常に人情家であることが分かる。そんな彼女の行動が後半、重要な意味になってくる。この性格の違う親子は皮肉を言い合いながら、約50年ぶりとなる父親の生まれ故郷での旅を続けるのだ。
ちなみに父親はこの旅にそこまで乗り気ではないものの、旅先で出会った女性とロマンスを楽しむほど気軽さを持っている。対して娘は、旅先でも別れた夫に無言電話をかけたり、ダイエットの為にジョギングをし、朝食も自前の種子のようなものを食べ続けている。やがて旅の目的がホロコーストを生き延びた父親や母親の当時の生活をルーシーが知る為だったと分かると、一気に胸が締め付けられるのだ。
何故、この旅を娘は思い付いたのか。きっとそれは父親の心の穴に気づいていたのと、自分に隠している当時の記憶を探ることで、父親と近づけると思ったからではないか。それが彼女の寂しさの原因だったのか。逆に父親は何故、娘とちゃんと向き合おうとしなかったのか。映画のラスト、そのすべてが明かされた時、言葉では言い表せない愛情の本質を見た気がした。そしてこの映画の原作がリリー・ブレットの実体験がベースとなる小説だと知ると、尚更、深く傷つけられた心はそう簡単に克服出来ないし、戦争は何世代にも影響を及ぼす痛烈なものだと再認識するのだ。