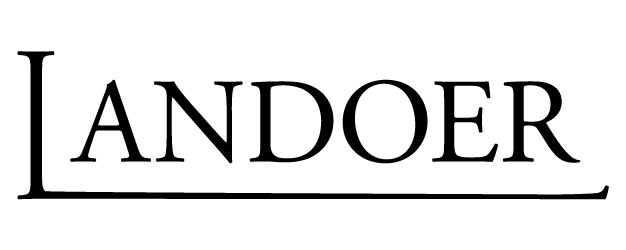「私」とは、「人間」とは、
その目覚めを考えたい貴方へ

-Introduction-
「女王陛下のお気に入り」のヨルゴス・ランティモス監督とエマ・ストーンが再びタッグを組み、スコットランドの作家アラスター・グレイの同名ゴシック小説を映画化。2023年・第80回ベネチア国際映画祭コンペティション部門で最高賞の金獅子賞を受賞した。
-Story-
不幸な若い女性ベラは自ら命を絶つが、風変わりな天才外科医ゴッドウィン・バクスターによって自らの胎児の脳を移植され、奇跡的に蘇生する。「世界を自分の目で見たい」という強い欲望にかられた彼女は、放蕩者の弁護士ダンカンに誘われて大陸横断の旅に出る。大人の体を持ちながら新生児の目線で世界を見つめるベラは時代の偏見から解放され、平等や自由を知り、驚くべき成長を遂げていく。プロデューサーも務めるストーンが純粋無垢で自由奔放な主人公ベラを熱演し、天才外科医ゴッドウィンをウィレム・デフォー、弁護士ダンカンをマーク・ラファロが演じる。「女王陛下のお気に入り」「クルエラ」のトニー・マクナマラが脚本を担当。
伊藤さとり’s voice

まるで新世界のアミューズメントパークを見せられているかのような映像。衣装も建造物もアートそのものであり、ただそこに存在する人々は、本能剥き出しの理性を無くした人ばかり。そうだ、人間の本質なんてこれがベースであって、「学び」の上塗りが続けられた結果、知性を手にして言語も行動も脳からの指令で管理されているのだ。
映画は、ウィレム・デフォー演じる天才外科医によって誕生した無垢な幼児と言えるエマ・ストーン演じる主人公ベラが外の世界への好奇心から、マーク・ラファロ演じるドンファンと冒険の旅に出るところから進化していく物語だ。
デザインの美しさに目を取られていく中で展開されるベラの「目覚め」の最初は、「性への目覚め」、よって「快楽」を知り、露骨で野生的なベラの姿を観客は目にすることになる。そこから彼女は、男性が女性をハントする社会の構図を知るのだが、ある日、何故、女性は男性を選べないのか、と疑問を持つのだ。そう、本作は、女性目線から描く人間の進化すべてであり、「教養」とは、社会に出て様々な人と交流を深める中で知る、より快適に生き抜く為のヒントとなる武器なのだ。
昭和の時代は「女は馬鹿な方が良い」という言葉さえあり、学のある女性は結婚に苦労するとまで言われていた。実際、給料の高い一流企業に勤める女性たちの婚期は遅れていたし、「話を聞くのが上手い女」はモテるといった処世術まで広まった。
時代は令和に変わり、もはやそんな化石のような話し、と思いきや、ベラが口にした「女性も男性を選ぶ」時代でもなく、多くの企業や組織の上層部は男性で占められている。果たして男性目線ばかりの世界で「皆がより快適に生き抜く社会」になるのだろうか。
映画は、この問題をアートのような映像美とひとりの女性の脳の発達を描く形で、しっかりと斬り込んでいる。興味深いのはベラの創造主は男性の天才科学者だが、そもそもベラは女性として生まれ育っていて、彼により改造された女性だ。
本来、教養を持っていれば男女とも生きやすい世界にするだろう。だが男性ばかりが人選の権利を持てる時点で、女性特有の生理や出産、更にはマイノリティの人の生活は理解されづらくなる。本来は男女、マイノリティの人々が決定権を持つ立場にバランス良く配置されることが良いだろう。しかも権力を持つ人に気に入られれば、仲間になれると思う人は必ず現れ、よほど潔癖な上司でない限り、その道筋は欲望で穢されてしまう。映画は人間の支配欲が他者を不幸にすることにまで触れ、美しいはずの世界の欲にまみれた毒々しい思考まで露見させてしまう。これこそが「哀れなるものたち」=社会なのかもしれない。
それにしてもよくぞあの『アメイジング・スパイダーマン』のキュートなエマ・ストーンが、あの『ラ・ラ・ランド』の可憐なエマ・ストーンが、こんな大胆すぎる役をやったものだ。しかも彼女はヨルゴス・ランティモス監督と2017年から構想を練っていて、本作にプロデューサーとして当初から関わっている。オリジナルではなくゴシック小説が原作とはいえ、独創的な世界観、そして「女性の自立」をテーマにした現代に通じるメッセージから、第80回ヴェネツィア国際映画祭金獅子賞(最高賞)を受賞した映画『哀れなるものたち』。いや、このまま行くと、エマ・ストーンがアカデミー賞主演女優賞再びというのも夢ではない。
映画『哀れなるものたち』
2024年1月26日(金)ロードショー
出演:エマ・ストーン、マーク・ラファロ、
ウィレム・デフォー、ラミー・ユセフ、
ジェロッド・カーマイケル
監督:ヨルゴス・ランティモス
配給:ディズニー

All Rights Reserved.