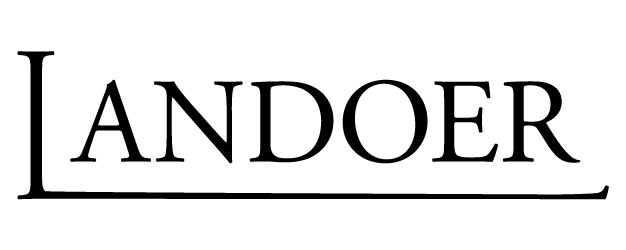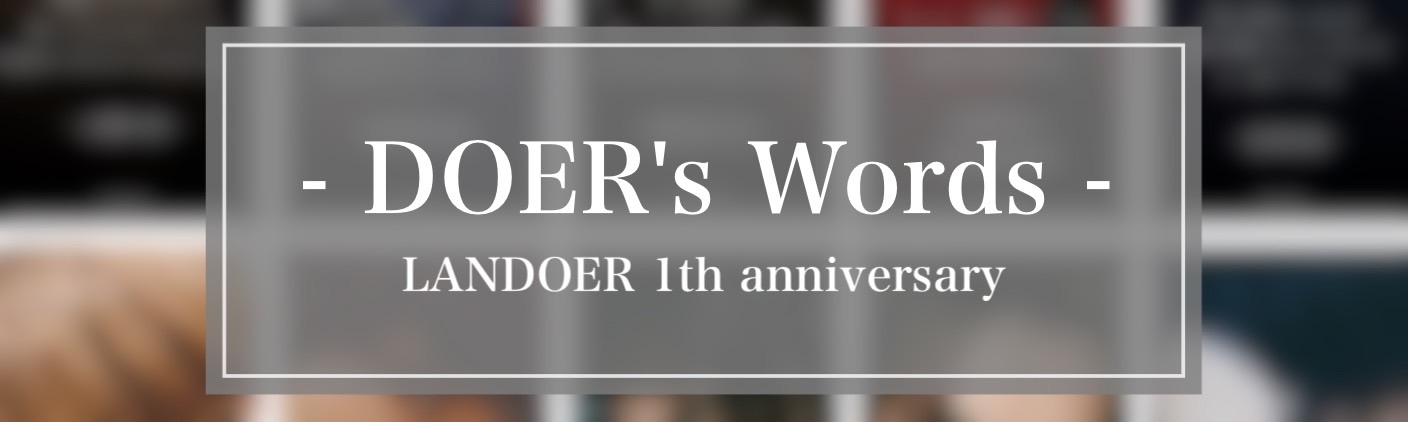映画『宝島』
日本の〝これまで〟と〝これから〟を紡ぐのは、
この島で生きるすべての私たち
声なき視点で「あの日」を見つめる2人の語り部対談
「なんくるないさ」⸺何とかなるさ、大丈夫という意味をもつ沖縄の言葉。あたたかい温度を纏うその言葉は、触れた心をそっと照らす穏やかな希望の灯火。しかし、火の産声に耳を澄ませば、沖縄の苦しく切ない歴程が聴こえてくる。それは、一つの目線からでは決して見えてこない史実の片鱗。一人ひとりに多面性があるように、私たちが立っているこの地にも多面的な〝歴史〟が存在している。教科書に書かれた、たった3行で済まされるような歴史など存在しない。では、私たちはどうやって「あの日」と向き合えばよいのか⸺幾つもの歴史ドラマや映画を手掛けてきた大友啓史監督、沖縄本土復帰を身をもって体験されたジョン・カビラさん。お二人に、史実との対峙、そして歴史を語り継ぐということについてお聞きしてまいりました。
映画『宝島』

-Introduction-
ある夜、一人の英雄が消えた。
アメリカ統治下の沖縄で、自由を求め駆け抜けた若者たちの
友情と葛藤を描く感動超大作。
戦後沖縄を舞台に、史実に記されてこなかった真実を描き切った真藤順丈による傑作小説『宝島』。審査委員から満場一致で選ばれた第160回直木賞をはじめ、第9回山田風太郎賞、第5回沖縄書店大賞を受賞し栄えある三冠に輝いた本作を実写映画化。監督を務めるのは、時代劇からアクション、SF、ドラマ、ミステリーやファンタジーまで、常に新たな挑戦をし続ける大友啓史(NHK大河ドラマ「龍馬伝」、『るろうに剣心』シリーズ『レジェンド&バタフライ』)。主演には妻夫木聡を迎え、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太ら日本映画界を牽引する豪華俳優陣が集結。日本に見捨てられ、アメリカに支配された島、沖縄。全てが失われ、混沌とした時代を全力で駆け抜けた“戦果アギヤー”と呼ばれる若者たちの姿を、圧倒的熱量と壮大なスケールで描く、サスペンス感動超大作が誕生!2019年に企画が動き出してから、6年の歳月を経て遂に公開となる本作。当初開発は順調に進み2021年にクランクイン予定だったが、度重なるコロナ禍に二度の撮影延期を経て実際にクランクイン出来たのは2024年2月。スタッフ・キャスト全員が「どうしても今の時代に届けたい」という強い情熱を持ち進んできたからこそ実現した奇跡のプロジェクトがついに公開。沖縄戦や、本土復帰後を描いた沖縄に関連する映画は過去にも多く製作されてきたが、本作は名匠・大友監督のもと<沖縄がアメリカだった時代>を真正面から描き切るかつてない“本気作”。実際に起きた事件を背景に進行する物語に、当時の状況を徹底的に調べ尽くし、リアルな沖縄を再現。クライマックスのシーンでは、延べ2,000人を超えるエキストラが投入され、その群衆一人一人にまで演出を加えていく大友監督により、当時の息遣いまで再現されたリアルな感情の爆発シーンなど、想像を遥かに超えたインパクトで描かれる。東映とソニー・ピクチャーズによる共同配給のもと、ハリウッドに拠点を置くLUKA Productions Internationalも製作に参加して日米共同製作で挑む、今までの常識を覆す、革新的なエンターテイメント超大作。
-あらすじ-
英雄はなぜ消えたのか?
幼馴染3人が20年後にたどり着いた真実とはー。
1952年、沖縄がアメリカだった時代。米軍基地から奪った物資を住民らに分け与える“戦果アギヤー”と呼ばれる若者たちがいた。いつか「でっかい戦果」を上げることを夢見る幼馴染のグスク(妻夫木聡)、ヤマコ(広瀬すず)、レイ(窪田正孝)の3人。そして、彼らの英雄的存在であり、リーダーとしてみんなを引っ張っていたのが、一番年上のオン(永山瑛太)だった。全てを懸けて臨んだある襲撃の夜、オンは“予定外の戦果”を手に入れ、突然消息を絶つ…。残された3人は、「オンが目指した本物の英雄」を心に秘め、やがてグスクは刑事に、ヤマコは教師に、そしてレイはヤクザになり、オンの影を追いながらそれぞれの道を歩み始める。しかし、アメリカに支配され、本土からも見捨てられた環境では何も思い通りにならない現実に、やり場のない怒りを募らせ、ある事件をきっかけに抑えていた感情が爆発する。やがて、オンが基地から持ち出した“何か”を追い、米軍も動き出す――。消えた英雄が手にした“予定外の戦果”とは何だったのか?そして、20年の歳月を経て明かされる衝撃の真実とは――。
監督・脚本 大友啓史
×
ジョン・カビラ


この時代に『宝島』を届ける意義
LANDOER:今、この時代に映画『宝島』を届けることについて、どのような意義を感じていらっしゃいますか?
大友啓史監督(以下、大友監督):もともと本作は、沖縄の本土復帰50年にあたる2022年の公開を目指していたのですが、コロナなどのさまざまな障壁を経て、期せずして戦後80年である今年の公開が決まったんです。戦後80年という節目の年には「戦争」そのものを見つめる企画——戦争という、国家間の衝突に一般国民が巻き込まれてしまう悲劇——に焦点を当てたものが、いくつか出てくるだろうと予想していました。けれど僕は、“戦争が終わった後に何が残るか”を伝えたかった。1945年に終戦を迎え、47年には日本国憲法が施行、52年のサンフランシスコ平和条約によって日本が国際社会に復帰した頃から、本土では経済的・人間的な豊かさが少しずつ重視されるようになっていきました。しかし、時を同じくして沖縄では『宝島』に描かれているような現実が存在していた。戦争が終わった土地では避けることのできない〈勝者と敗者〉、〈強者と弱者〉という構図が、アメリカと沖縄間で出現していたんです。沖縄の人々の“普通の生活”が、戦争によってどのような制約を受けていたのか。それは、戦争を経験していない我々が“生活”という側面から知ることのできる、戦争史の大切な一篇。本作を通じて、戦争というものが私たちの生活にどんな影響を与えるのか、その影響はどのくらい続き、そこでは一体何が起こるのか——そうした問いに触れていただけたら、それこそがこの作品の意義に繋がると感じています。
LANDOER:『宝島』の登場人物たちは、戦後の沖縄でとても強く“普通の生活”を求めていますよね。
大友監督:そうですね。彼ら彼女らは誰かに与えられた自由や平等、民主主義ではなく、自分たちで見出したものを、自分たちで戦って獲得しようと決意していくんですよね。僕は、そういった “人々が立ち上がっていくプロセス”を描くことこそが、本作をつくるうえで大切な視点だと思っていました。「戦争」と聞くと、どうしても戦闘の残酷さのみに目がいってしまいがちだけれど、戦いの後にも、勝った者と負けた者の間でさまざまな、「残酷な」現実が生みだされていく。さらには戦争によって、今まで考えられてきた社会の仕組みや世の中の価値観もどんどん変えられていってしまう。我々はそのとき、何を一番大切にして、大切なものとどう向き合い、どう立ち向かうのか——それはまさに、『宝島』の時代を生きた沖縄の人々が示してきた歴史だと思います。
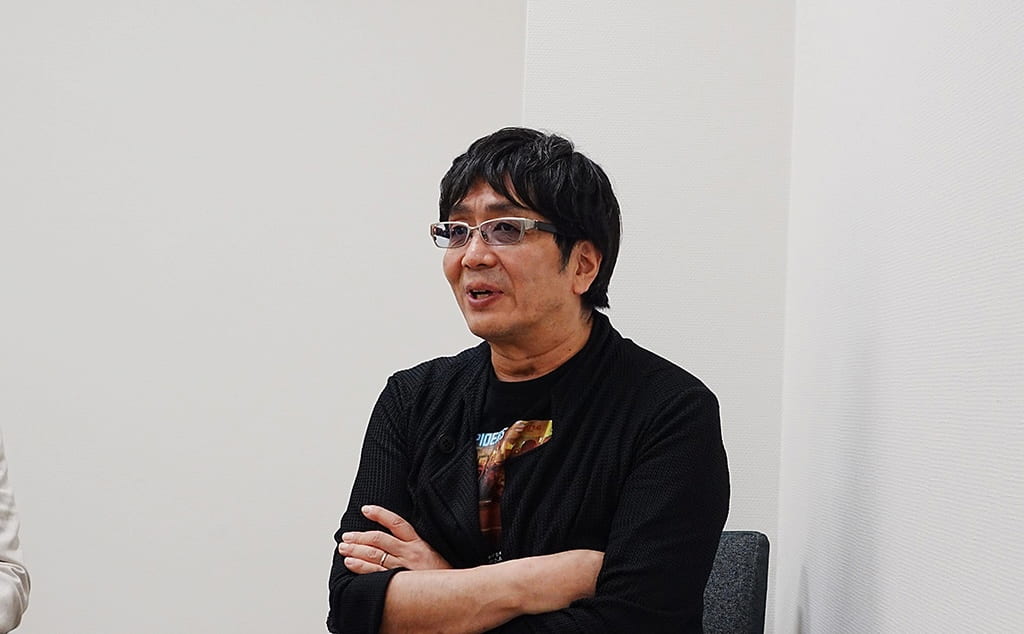
『宝島』には鼓動と血肉が宿っている
生ける教科書、ここにあり
LANDOER:『宝島』の舞台となった1952年から1972年の間、実際に沖縄で生活されていたカビラさんですが、この作品をご覧になってどのような想いを抱かれましたか?
ジョン・カビラ(以下、カビラ):「生ける教科書、ここにあり」と思いましたね。『宝島』という教科書には動きがあり、血肉がある。本当に感情を揺さぶられる作品だと思います。
LANDOER:カビラさんは、作中にも描かれている“コザ暴動”の号外を、当時現地でご覧になっていたんですよね。
カビラ:そうなんです。だから、僕にとって『宝島』で描かれている1952年から1972年までの20年間は、自分の個人史でもあるんですよ。1952年は、僕の父がNHKのアナウンサー研修所に志願した年で、1972年は、学校のホームルームで担任の先生に「本土復帰を果たしたけれど、米軍基地の存在は変わらない」旨の話を聞いた年。どちらも自分にとってシンボリックな年なんです。
LANDOER:まさに個人史と作品の舞台が重なっているんですね。当時の日本、そして沖縄の雰囲気をどのように記憶されていますか?
カビラ: 1953年、サンフランシスコ講和条約締結にあたり、大手新聞社の社説で「日本はドイツや朝鮮半島違って、国土を分かつことなく平和と独立を得る」といった表現がされたのですが、当時はまだ、沖縄も小笠原諸島も奄美大島も本土から“分かたれていた”んです。敗戦したのち、戦争の総括が十分にされないまま戦後がはじまり、講和条約のもと独立を果たした一方で、沖縄が“分かたれたまま”であることは見過ごされてしまっていた。当時はそうした意識の齟齬という現実が本当にあったんです。
LANDOER:まさに個人史と作品の舞台が重なっているんですね。当時の日本、そして沖縄の雰囲気をどのように記憶されていますか?
カビラ: 1953年、サンフランシスコ講和条約締結にあたり、大手新聞社の社説で「日本はドイツや朝鮮半島違って、国土を分かつことなく平和と独立を得る」といった表現がされたのですが、当時はまだ、沖縄も小笠原諸島も奄美大島も本土から“分かたれていた”んです。敗戦したのち、戦争の総括が十分にされないまま戦後がはじまり、講和条約のもと独立を果たした一方で、沖縄が“分かたれたまま”であることは見過ごされてしまっていた。当時はそうした意識の齟齬という現実が本当にあったんです。

LANDOER:伺っていると、戦後の沖縄が置かれていた状況がいかに複雑で、歴史のなかで見過ごされがちだったのかが分かります。
カビラ:1972年の本土復帰は素晴らしいことだったけれど、「米軍基地は残されたまま」「ひょっとすると核兵器も残ったままかもしれない」といった、住民の不安は拭いきれていなかったと思います。沖縄の人たちのやさしさや熱さの裏にある、不安や憤りを含む苦く切ない歴史と葛藤。大友監督は、それらをとても丁寧に描かれていると感じました。作中に『金門クラブ』(サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジを船でくぐった日本人留学生たちによって結成されたクラブ)というクラブが登場するのですが、実は、僕の父は金門クラブのメンバーだったんですよ。映画でもそのクラブを描いてくださったことがとても嬉しくて。父と一緒に必ず観に行こうと思っています。
LANDOER:カビラさん、そしてお父様のような、当時を生きた方々にこの作品が届いていくことも、本作の大きな意義の一つだと感じます。
カビラ:こうしてお話ししていても胸が熱くなるほど、僕にとって『宝島』の物語はとても個人的なものなんです。本作を通して浮かび上がってくる「本当に日本は戦争犯罪を裁いたのか」といった問いなどは、なかなか語られる機会がないじゃないですか。しかし、これらの歴史は決して遠い昔の話ではなく、今なお続く基地の扱いをめぐる議論や、事件・事故への捜査権の問題、さらには、東京の空の一部の空域を日本が管制できていない現状にまで繋がっているんですよ。そういった意味でも、いまだ戦後の課題は続いたままなんです。この作品は、その事実を赤裸々に描きつつ、同時にヒューマンドラマとしても魅せてくれる本当に素晴らしい映画だと思います。

こもる時代に、拓かれる物語を——
『宝島』が描く、“身の回り主義”を超えてゆく意志
LANDOER:歴史は地続きで繋がっていますが、一人ひとりの感性や生き方は、時代とともに大きく変化しているように思います。大友監督は現在(いま)の社会に流れる雰囲気を、どのように感じていらっしゃいますか?
大友監督:個人的には、コロナ以降いろいろな風向きが変わったように感じています。特に痛感しているのは“こもった感覚”の広がり。コロナ禍で、誰もがこもらざるをえない日々を経験したことで、もともとあった “コンビニ主義(=身の回り主義)”が進行していったといいますか。それが〈感性〉として進んでしまった気がするんです。
LANDOER:“コンビニ主義”、現代の日本人には特に強く感じますね。
大友監督:日本って平和だから、自分の身の回りのことだけを考えていれば、半径50メートル圏内だけでも幸せに生きていける国だと思うんです。その範囲内で考える物事は、とても平和で治安もいい。いろいろなことが認められているし、自分の好きなことを好きなだけやってもいい。でもそこに甘んじてしまうと、自分の好きなものに関する情報だけしか寄ってこなくなるんですよね。そしていつの間にか、自分の範囲外の情報を取りにいかなくなってしまう。正直、寄ってくる以外の情報を取りにいくのって、ものすごく労力を使いますし、強い意志が必要なんですよ。だったら、自分の好きなもので周りを埋めているほうがラクで幸せじゃないですか。そうした〈感性〉が、コロナ禍で一層強まったように感じます。
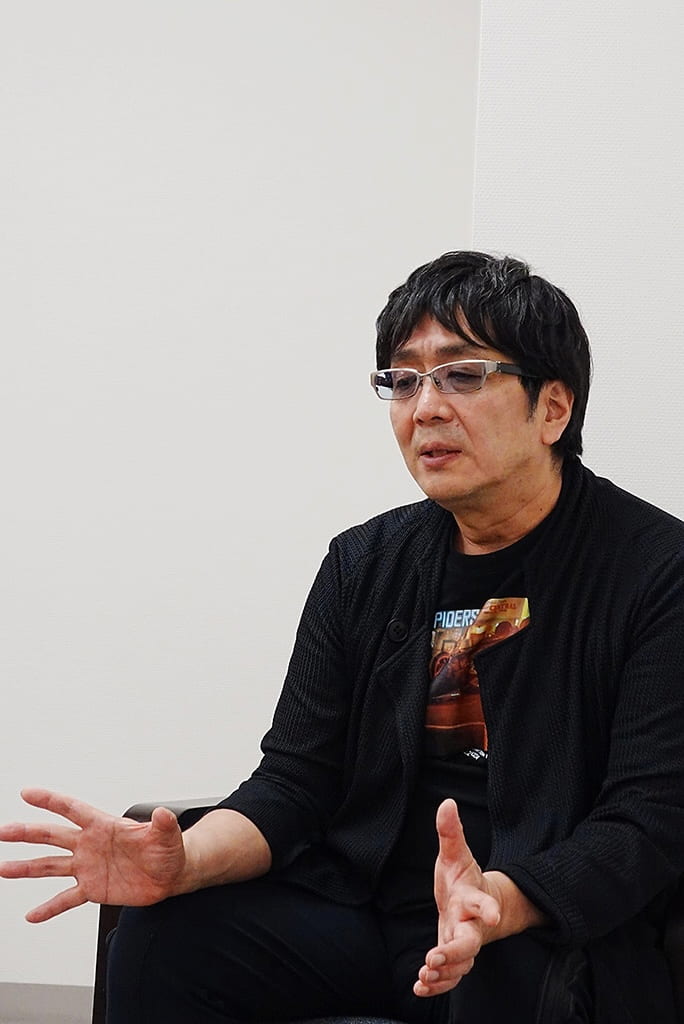
LANDOER: 本当にそうですよね。ネットを見ていても、アルゴリズムによって自分に最適化された情報ばかりが届く時代ですし。
大友監督:“コンビニ主義”は年代問わずだと思っているけれど、何だかんだ僕ら昭和世代は「拡げていく」ということを、とても大切にしてきた気がするんです。戦後の民主主義が活発だったこともあって、自分の身の回りだけでなく、海の向こうで起きている出来事にも心を痛めて、声を上げることの価値を社会全体で認めてくれていたし、背中を押してくれていた時代でもあったんですよね。
LANDOER:現代は「声を上げる=思想的」と結びつけられがちで、あえて沈黙を選ぶ人も目立つように感じます。
大友監督:SNSやコンテンツの世界を見渡すと、「どんどん外を向いていこう」という感覚が生まれはじめているように思えるのですが、一方で “ドメスティックな身の回り主義”が根強く残っているのも、現代社会の特徴だと感じます。だからこそ僕は『宝島』に描かれているような感覚、人と人が直接ぶつかり合い熱を生み出していくという、そういう身体性という概念も含めたスタンスが今一度現代人には必要だと思っていて。「今こそ必要な〈感性〉が、『宝島』にはある」という想い、そしてそれを届けたいという熱量が背中を押し続けてくれたから、本作を最後までやりきることができました。

歴史は、“自分の背中を押してくれるもの”
崇め奉るのではなく、自分事として向き合って
LANDOER:『宝島』では、語り部(ユンター)や御嶽(ウタキ)、ユタの人々など、“継いでいくこと”の尊さと大切さが描かれています。そして、今を生きる私たちもまた、戦争の歴史を次の世代に語り継いでいかなければなりません。そのために必要なのは歴史を知ること。お二人は史実を集める際に大事にされていること、注意されていることはありますか?
大友監督:歴史ドラマを作っている立場から言うと、史実と向き合う際に「創作が含まれているかもしれない」という視点を常にもつことが、とても大事だと思います。史実に残っているものって、当時、余裕があった人たちによって記されたものが多いんですよ。なぜなら、ほとんどの人は記す余裕がないまま人生を終えていくから。坂本龍馬なんかは分かりやすい例で、彼は特別な地位にあった人ではないただの脱藩浪人で、その手紙は百通以上残されていますが、代表的な一次資料は姉に宛てた手紙がほとんどなんですね。龍馬はやがて、「日露戦争の開戦前に皇后さまの枕元に立った男がいた、それが龍馬だった」ということがまことしやかに囁かれ、護国の神として扱われるようになります。大正時代になると、今度は土佐の新聞で「自由民権運動を体現した男」という立ち位置で主人公化された。そして高度経済成長期には、司馬遼太郎さんが『竜馬がゆく』で龍馬を描き出し、彼を“永遠の青春像”として定着させていった。この一連から分かるように、歴史に残る人々には、少なからず創作が加わっているんですね。それはある意味、個人の主観やその時代の集団願望の投影でもあって。では、その解釈の過ちを突き止めるのか?それは歴史学者の仕事であって、僕らの仕事ではない。だからこそ個人的には、「歴史は自分にとって都合よく使っていいんじゃないか」と開き直って思うところがあるんですよね。むろんそれは、好き勝手に、という意味ではありません。こうやって創作して皆さんに届けるという作業においては、調べられるものをとことん調べる、というスタンスは絶対的に必要です。一方で歴史上の人物たちやその業績を神格化するのではなく、そういう精神性に陥らないように、ある種歴史上の人物を常に自分と同じ人間として相対的に見る。そうすることで、歴史が背中を押してくれることもあるんじゃないかな、と。

LANDOER:たしかに自分事として歴史に触れると、ぐっと向き合いやすくなりますね。
大友監督:過去のすごい人たちを崇め奉るために歴史を学ぶのではなく、“自分の背中を押してくれる生き方をした人”を知るために歴史を学ぶ、という姿勢でいることが大事だと思います。戦争の歴史に関しても、過去をネガティブに批評するのではなく、むしろ「先人がこういうことを間違えた、こういうことをしてきたのだから、僕たちはこうしようね」と、自分の生き方に歴史を取り込んでいってほしいんです。そうした視点から史実を見ないと、あっという間にその反動で誰かを崇め奉るほうにいってしまう気がします。
LANDOER:歴史に血肉や鼓動を感じる、まさに『宝島』を通して触れられる史実の姿だと思います。
大友監督:過去の人物の所業を断罪するだけでは、前には進めないですからね。生きている人間は、みなその都度その立場で必死の判断をしているはずです。当時の時代の空気をまといながら、ある者はその流れに乗り、そしてある者はそれに抗って生きている。教科書に書かれている結果論だけでイエス・ノーを考えていると、その裏に隠されている事実、そこで生きていた人々の感情を見落としてしまう気がします。それこそ、サンフランシスコ講和条約で多くの人が喜んで、日本が国際社会に復帰した時代を沖縄の目線から考えると、『宝島』に描かれているような、全く異なる事実が見えてくるわけです。大切なのは、一つの歴史とどう距離をとって、どんな立ち位置から見るのか——その意識をもって史実に触れてほしいと思います。そういう意味では、今回描いた“戦後の沖縄”はとても難しい題材でした。ただそれと同時に、歴史の立ち位置や、私たちが見過ごしてしまいがちな視点を教えてくれるものでもありました。沖縄という土地は、“声なき視点”に気づかせてくれる場所なんです。

Dear,これからの未来を創るLANDOER読者へ
LANDOER:これから「戦争」という歴史を語り継いでいかなければならない私たち。今、自分にできることは何だと考えていらっしゃいますか?
カビラ:個人的には、スマホなどを用いて記録に残していくことが大事だと思っています。僕の場合は折に触れて、父親に戦前・戦中・戦後の沖縄、そして広く日米の話を聞いて録音するようにしているんです。またありがたいことに、ラジオ番組のお仕事を通じて、父との対談企画を任せていただけたりもして。自分の立場で何ができるのかを考えて、ずっと発信し続けていくことを大切にしていけたらと思います。
LANDOER:ご両親の個人史をご自身ができることで広げていく——カビラさんのお話をお聞きして、たとえどんな仕事をしていても、自分にできることを考えるだけで“伝え方”が見えてくるような気がしました。
カビラ:そうですね。ラジオやメディアでなくとも、皆さんのおじい様やおばあ様、ご両親に当時のお話を聞くだけでもいいと思います。そしてその話を記録に残しておいて、“生きる個人史”として次の世代に繋いでいく。それが“語り継ぐ”ということなんじゃないかな、と。もしかしたら、お話したくないという方もいらっしゃるかもしれませんが、「当時、嬉しかったことは何だった?」「流行っていた歌は何だった?」といったライトなテーマから聞いていくと、いろいろなお話が出てくると思います。
大友監督:この話はかなり有効だね(笑)。
LANDOER:とても参考になります!
カビラ:いえいえ(笑)。あ、あともう一つ!今ってみんな、個人のことをSNSで発信しているじゃないですか。僕、あれをおじいちゃんおばあちゃんでやったらいいと思うんですよ。現代は、非常に素晴らしい発信ツールに溢れている時代ですし、メディアの民主化もされてきているわけですから。「あなたのアーカイブ」「あなたのファミリーヒストリー」という形で世の中に届けていくことを、心からおすすめします。
大友監督:新しい世代の皆さんは、僕らが受けてきた戦後の民主主義教育を通ってきていない分、最初からフラットな立場で戦争を語ることができる世代だと思うんです。大人たちは「どっちの味方なんだ」と色をつけたがるかもしれないけれど、あくまで個人史として歴史に触れて、そこに出てきた人たちの感情を、物語を見つめるように受け取っていってほしいと思います。(お隣りのカビラさんに)若い世代の方々にも、こういった議論をどんどんしていってほしいですよね。
カビラ:そうですね。お願いしますよ!
映画『宝島』
妻夫木聡さん×窪田正孝さんの
対談インタビューはこちら

大友啓史
おおとも けいし
1966年、岩手県生まれ。1990年にNHKに入局し、連続テレビ小説「ちゅらさん」シリーズ(01~04)、「ハゲタカ」(07)、「白洲次郎」(09)、NHK大河ドラマ「龍馬伝」(10)などを演出。イタリア賞はじめ国内外の賞を多数受賞する。2009年、『ハゲタカ』で映画監督デビュー。2011年に独立し、『るろうに剣心』(12)、『プラチナデータ』(13)、『るろうに剣心 京都大火編/伝説の最期編』(14)、『秘密 THE TOP SECRET』『ミュージアム』(16)、『3月のライオン』2部作(17)、『億男』(18)、『影裏』(20)など話題作・ヒット作を次々と世に送り出す。『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』(21)では、2部作合わせて70億円、シリーズ累計200億円に迫る大ヒット。東映創立70周年記念作品の『レジェンド&バタフライ』(23)は、20億円を超える興行収入を記録。

ジョン・カビラ
1958年 、沖縄県生まれ。大学卒業後はCBS SONY(現ソニーレコード)入社。海外との渉外部門に所属し、レコードの資材輸入やアーティストプロモーションのコーディネートなどを担当する傍ら、テレビ番組などでミックジャガーやボズスキャッグス、TOTOなどの通訳も経験。1988年J-WAVE 開局と同時にナビゲーターに転身。2005年に第42回ギャラクシー賞DJパーソナリティー賞を受賞し、2010年には第47回ギャラクシー賞ラジオ部門大賞を受賞。また、2020年に第57回ギャラクシー賞ラジオ部門大賞と日本民間放送連盟賞ラジオ・グランプリを受賞。2025年にはギネス世界記録「サッカービデオゲームコメンテーターの最多出演数」を保持し、スポーツ番組MC、情報番組MC、テレビ、CM、雑誌、舞台など活躍の場を広げる。
映画『宝島』
全国公開中
出演:妻夫木 聡
広瀬すず 窪田正孝
中村 蒼 瀧内公美 / 尚玄 木幡竜
奥野瑛太 村田秀亮 デリック・ドーバー
ピエール瀧 栄莉弥
塚本晋也 / 永山瑛太
原作:真藤順丈『宝島』(講談社文庫)
監督:大友啓史
配給:東映/ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

Staff Credit
インタビュー・記事:満斗りょう
ページデザイン:Mo.et