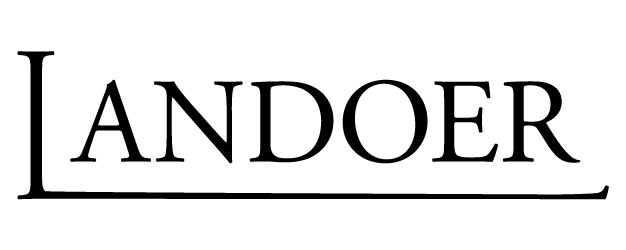パルコ・プロデュース2025『シャイニングな女たち』
念願の初タッグで描くのは
主観と客観に翻弄される女たちの物語
闘う女と、紡ぐ男のシャイニングなスペシャル対談
「光と闇はともにある」というけれど、光の裏で女たちが生み出す〈闇〉には、もっと多くの呼び名がある。矛盾、孤独、依存、執着―それらをまるっと〈闇〉なんて言葉で括られちゃ、たまったもんじゃない。純粋な光よりずっと強く、歪に輝く〝本性〟を潜め、今日も生きている私たち。社会という荒波に抗いながら、幾重にも重なる葛藤と闘いながら、時に上手く笑顔を浮かべながら。けれど、ふと思う。この荒波も葛藤も、私が生み出したものだとしたら―···? 自分しか信じられない世界で、主観の不確かさが浮き彫りになってゆく。これぞまさに〝蓬莱ワールド〟。シャイニングな女たちの闘いが、世に放たれるまであと少し⸺。
パルコ・プロデュース2025『シャイニングな女たち』

-Introduction-
吉高由里子×蓬莱竜太 念願の初タッグがここに実現!
一人の女性の死を巡り
孤独な現在と輝かしい過去が交錯していく
生きづらい女性たちの今を描く群像劇
少しずつ少しずつ何かが削られていく―
現代社会の生きづらさと
「主観の不確かさ」を描く蓬莱竜太の新作
日常に潜む人間の葛藤や矛盾を丁寧に掬い取り、鋭い視点の中にユーモアを織り交ぜる作風で多くの観客の共感を呼んできた蓬莱竜太。1999年に劇団モダンスイマーズを旗揚げし、劇団公演のみならず、数多く手掛ける外部公演でもその手腕を発揮しています。2016年には『母と惑星について、および自転する女たちの記録』で第20回鶴屋南北戯曲賞、2019年には『ビューティフルワールド』で第27回読売演劇大賞優秀演出家賞を受賞するなど、作・演出の双方で数々の受賞歴を誇ります。パルコ・プロデュースの公演では2023年に脚本・演出を務めた『ひげよ、さらば』以来2年ぶりの登場となります。本作は、主人公たちが社会人として働く現在と、大学時代の過去とを行き来しながら、人間関係のもつれやSNS時代に生きる私たちの光と闇を浮き彫りにする女性たちの群像劇です。一人の女性の死をきっかけに浮かび上がる記憶の齟齬が、美しかったはずの思い出を歪ませていく―――現代社会に潜む矛盾や孤独を、繊細かつ圧倒的な筆致で描きます。直接的なコミュニケーションが希薄となった現代において、誰もが当事者になりうる物語であり、観客自身の体験を呼び起こすことで「自分ならどう向き合うか」を問いかけます。社会的テーマに鋭く切り込みながらも、キャラクターの魅力とユーモアで観客の心をつかんできた蓬莱の最新作に、ぜひご期待ください。
-Story-
金田海(吉高由里子)は、社会人として働く傍ら、他人のお別れの会に紛れ込み、ビュッフェを食べて帰るという行為を繰り返していた。ある日、入り込んだお別れの会の会場で金田は偶然見覚えのある顔たちに出会う。それはかつて自分がキャプテンを務めていた大学時代の女子フットサル部の仲間たち。親友の山形圭子(さとうほなみ)の姿。敵視していた顧問の川越瑞希(山口紗弥加)の姿まであった。遺影には同じピッチに立っていた後輩、白澤喜美(桜井日奈子)の姿。『私は何故呼ばれていないのか』お別れの会の会場と輝いていた大学時代が交錯していく。その輝きは本当の輝きだったのか——。
金田海役 吉高由里子
×
作・演出 蓬莱竜太
主演 吉高由里子
×
作・演出 蓬莱竜太
LANDOER:吉高さん念願の蓬莱作品ということで、出演が決まったときのお気持ちを教えてください。
吉高由里子(以下、吉高):「叶ってしまった…!」と思いました。いまは、嬉しさと同時に恐ろしさも感じています。
LANDOER:吉高さんは、蓬莱作品のどんなところに魅力を感じられてきたのでしょうか?
吉高:観終わったあとに、ちゃんと傷つくところですかね。自分のなかで酸化していた感覚を呼び戻されるといいますか。それは時に苦しかったりもするのですが、どこか慣れてしまっていた自分にハッとさせられたり、気づかされたりすることのほうが多くて。初めて蓬莱作品を観劇したとき、その刺激にとても魅力を感じたんです。
LANDOER:蓬莱さんが今回の吉高さんとのタッグで期待されていること、また、吉高さんにもたれている印象を教えてください。
蓬莱竜太(以下、蓬莱):まずは純粋に楽しみです。演劇はだいたい「初めまして」からはじまり、一ヶ月間の稽古と、さらに一か月間の本番期間を経て、終わる頃にはお互いを深く知ることができているもので、僕はその“時間”がとても好きなんです。今回、吉高さんと同じ時間を共有できることにワクワクしています。

忘れていた「あの瞬間の自分」を思い出させる、
蓬莱作品ならではの“無意識の暴力”
LANDOER:吉高さん演じる『金田海』は、他人のお別れの会に出席してビュッフェを食べるという、一風変わった趣味の持ち主ですが、蓬莱さんがこの設定を思いついたきっかけはなんだったのでしょうか。
蓬莱:実際に「他人のお別れの会に勝手に出席する方がいる」というお話を聞いたことがあって、「そんな人がいるの?」と(笑)。
LANDOER:まさか、実際にあるお話だったんですか!
蓬莱:そうなんです(笑)。その話を聞いたときに、ふと「他人のお別れの会だと思って出席した会が自分の知人のお別れ会で、しかも自分が呼ばれていないことに気づいたらどうなるんだろう」と思ったんですよね。そしてその“呼ばれなかった女性”を吉高さんに演じていただけたら、とてもワクワクするだろうな、と。現代社会の何かの隙間にふっと差し込まれているような、そうせざるをえない心理状態の人が、そんな状況に陥ってしまったらどうなるのかが気になって。そこから話が膨らみそうな気がして、この設定を出発点にさせていただきました。
LANDOER:吉高さんは、設定を読んでどう感じられましたか?
吉高:まさか本当に『海』のような人がいたことに、いま驚いています(笑)。私自身、学生時代に同級生が交通事故で亡くなり、お葬式に参加したことがありました。正直あまり話したことのない人だったのに、そのときなぜか涙が出てきたんです。目の前に魂が抜け落ちた肉体だけがあるという現実、その人はもういないのに、生きている自分と肉体同士は対峙しているという不思議な感覚に戸惑ったのだと思います。海が他人のお別れの会に出席する場面で「見知らぬ人でも何故か痛みのようなものを感じる」という描写があるのですが、それを読んだときに、“悲しい”とはまた違う、あの奇妙な感覚を思い出しました。蓬莱さんって、こういうふうに忘れていたことをいきなり思い出させてくるんですよ!
蓬莱:思い出させようとしているわけじゃないですよ(笑)。
吉高:もちろん意図はしていないと思うけれど、蓬莱さんの作品には、そういった“無意識の暴力”があるんですよ。

いわゆる“いい人”ではない側面を描くおもしろさ
はたして彼女は、善か悪か——
LANDOER:吉高さんを主演に迎えることが決まり、作品や人物の描き方に何か変化はありましたか?
蓬莱:そうですね、『海』の輪郭がさらに鮮明になったような気がします。吉高さんには、“非常に素直で魅力的な芝居をされる方”という印象を常々もっていたので、今回はその魅力を『海』につなげたいと思いました。僕のなかで描きたかった『海』のイメージは「人に迷惑をかけている人」。それこそ、本人は良かれと思ってやっているのに、結果的に“無意識の暴力”を発露してしまっているような。吉高さんの芝居がもつ魅力と、海という人物のキャラクター性が重なることで、新たなおもしろさが生まれるのではないかと期待しています。
LANDOER:吉高さんがおっしゃっていた蓬莱作品の魅力が、すでにキャラクターにしっかりと浸透しているようで楽しみです。
蓬莱:いわゆる“いい人”ではない側面、ある人からすれば“いい人”だけれど、ある人にとっては強い被害を受けている人、そんな、はたから見ると「どっちなんだろう?」と思わせるような人物にしたくて。ただ、『海』自身はそういったことにはまったく無頓着。そこがまた、おもしろくなるだろうと思っています。
LANDOER:蓬莱さんは、本作の公式コメントで吉高さんのことを「闘いから逃げない強さと、しなやかな明るさを感じる人」だとおっしゃっていましたが、吉高さんはご自身ではどのように感じられますか?
吉高:何もしなやかなところなんてないです。ビビり散らかしています(笑)。いまはただ、なるべくセリフを減らしてくださることを願っております(笑)。
蓬莱:あはは(笑)。
吉高:台本の序盤を読ませていただいたときに「スローモーションで走る」というト書きが書かれていたのですが、これまでスローモーションで走ったことなんてないんですよ。タイトルバックの時点で、すでにやったことのない動きが書かれていたので、「この先、何をさせられるんだろう…」と怯えています(笑)。きっと、いろんな挑戦が待ち構えているんだろうなと思っているところです。

これからの世界を生き抜いていかなければいけない、
そんな女性たちには“ドラマ”がある
LANDOER:公式コメントで、蓬莱さんは「女性は否応なく闘わなければならない」とおっしゃっていましたが、具体的に女性はどのようなものと闘っていると感じられていますか?
蓬莱:まずはやっぱり、“男性社会”との闘いですよね。これは太古から続いているものだと思うのですが、女性は「機嫌がよくなければいけない」と求められたり、美醜のことで差別を受けたりと、常に男性社会のなかで闘いにさらされてきたと思うんです。同時に、自分の居場所やアイデンティティを見つけなければ、勝手に“不幸な女性”だとみなされてしまう。さらには「この幸せでなければいけない」といった、“定義づけられた幸せ”や“充実した生き方”を押しつけられることも多い。内的な闘いというより、常に外側から闘いを要求されている印象があります。
LANDOER:今回、女性の闘いを描こうと思われた理由はなんだったのでしょうか?
蓬莱:そんな“強いられる”ことが多い社会のなかでも、女性のみなさんはそれぞれにいろんな闘い方をされているな、と思ったんです。僕は、そういった姿を作品にしたくて。個人的な話をすると、うちの劇団員たちは僕と同じ年齢の男性ばかりなのですが、僕らくらいの歳の男性になると、もうあまりドラマが生まれなくなってくるわけですよ(笑)。だからこそ、若い人や女性など、これからの時代を生き抜いていかなければいけない人たちに、ものすごくドラマを感じたんです。
LANDOER:そういった闘いから、吉高さんは「逃げない女性」というイメージなんですね。
蓬莱:そうですね。逃げないというか、闘っているのか、泳いでいるのか…そのあたりが読みとれないほど、僕にはしなやかに見えるんです。そういった吉高さんの在り方が、異性・同性を問わず、彼女を魅力的に感じる大きな要因なのかなと思います。
吉高:一番いい言葉で飾っていただいていますが、のらりくらりやっているヤツだと思われているのかもしれないです(笑)。
蓬莱:あはは、違いますよ(笑)。
LANDOER:吉高さんは、女性として闘ってきた実感はありますか?
吉高:私自身は、男尊女卑を目の当たりにしている世代ではないのですが、男性が立てられる、あるいは男性を立てなければいけない場面は見てきました。とはいえ、そういったものと闘っている分、男性が経験できないような得をしてきた部分もあると思うんですよね。男性か女性か、どちらがいいかと言われると難しいけれど、人生の後半が男性だったら楽しいのかなと思ったりもします。あ、だけど、旦那さんが亡くなったあとの女性の輝き方ってすごいものがある方もいますよね。だから、やっぱり女性…?難しいですね。みんなに「来世は男性がいいか、女性がいいか」というアンケートをとりたいです(笑)。

女性特有の組み方、
それは一種の依存か、恋愛か——
美しさを求めるほどに、歪に輝く女たち
LANDOER:本作では、男性と女性の闘いのみならず、女性同士の闘いも繊細に描かれるのではないかと思います。蓬莱さんが女性同士の闘いについて抱かれている印象や、実際に目の当たりにしたことがある女性たちの闘いがあれば教えてください。
蓬莱:うちの母親が三姉妹で、子どもの頃から母たち三姉妹が延々と話しているのを見ていたのですが、全員がお互いの話をまったく聞いていないんですよ(笑)。それを見たときに、女性のすさまじさを感じたことを覚えています。あとは、高校時代、女子生徒が多い学科に通っていたので、クラスの女子たちの妙な喧嘩なんかもよく見ていました。母たちやクラスメイトの女子たちの姿を見ていて、“男性とは違う在り方”があるのだということを、実体験として感じていましたね。
LANDOER:異性という外からの目線で見ても、女性って複雑なんですね。
蓬莱:なんか、おもしろいんですよね。たとえば、お互いに「親友だよね」と確認し合っているのに、ポロッと文句を言っていたり。もちろん、親友=文句を言わないというわけではないと思うのですが、女性同士の親友観や複雑さには、男性とは違うものがあると感じます。男性の友達って、常に一緒にいる必要がないというか、関係性に距離があるんですよ。それに比べて、特に学生時代の女性たちは、僕らにはわかりえない特有の関係の組み方を築いていて。この作品にも、そんな特有の関係値が多分に組み込まれているはずです。
LANDOER:吉高さんは、女性特有の組み方の内輪にいる身として、女性同士の闘いをどう見ていますか?
吉高:学生時代、周りの女友達たちを見て、一種の依存関係や恋愛に似通ったものを感じていました。あの頃はそれぞれが、女友達との在り方・つながり方によって、自分の立ち位置や求められている感覚を実感していたんだろうと思います。それってたしかに歪だと思うのですが、なんかこう、美しさって求めれば求めるほど歪になっていったりするじゃないですか。だからきっと、誰もがその小さな世界のなかで、自分なりの“シャイニング”を探していたんだと思うんです。あと、さっき蓬莱さんがおっしゃっていた三姉妹の話もとてもよくわかります(笑)。
蓬莱:わかっていただけます(笑)?
吉高:すごくわかります。この間、母と二人でごはんに行ったのですが、おばちゃんって本当に人の話を聞いていないんですよ(笑)!聞いていないのに質問してくるし、答えたときにはもう違う話をしているし…。「なんで聞いたんだろう?私はどこまで真剣に答えたらいいんだろう?」と思って、言葉で言い表せない疲れ方をしました(笑)。母ひとりでも大変なのに、3人もいたら本当に大変だろうと思います(笑)。

“寿命のない世界”で息をするアカウントたち
増し続ける、放つ側と受け取る側の難しさ
LANDOER:今回は、物語にSNSも絡んできますよね。蓬莱さんは社会におけるSNSの存在をどのように位置づけられていますか?
蓬莱:SNSが出てきて、いろんなことがずいぶんと変わりましたよね。個人的には「厄介なものが生まれたな」と思いつつ、情報を拡散するという点では優れた部分も感じていて。ただ、“匿名性を保ちながら自分の承認欲求を満たせるツール”という、現代の穴をついているその仕組みには、強い依存性を生み出す危うさもあると思っています。現実の自分とは違う自分をつくり出すことで自己実現を果たせるようになれば、非常に怖いものが生まれる可能性だってあるわけじゃないですか。そして、そういった投稿を受け取る側の情報処理の仕方もどんどん難しくなっていく。たとえば、真実かどうかわからないものが誤認され広がっていく過程で、一歩情報処理を誤れば、そこに関わる人の人格を外部が勝手に形成してしまうことだってあるかもしれない。それってとても怖いことだと思うんです。
LANDOER:“学生時代”という制限されたコミュニティのなかで投稿される情報には、さらに濃い密度を感じます。今回はSNSをどのように登場させたいと考えていますか?
蓬莱:今回は、大学時代にフットサルチームで“輝き”をつくれたと思っていた裏で、実はまったく違う現実がつくられていた——そんな、主観と客観について描きたいと思っているんです。いつの間にか当事者自身もそれらの境界線がわからなくなっていくような物語にしたいな、と。SNSは、そういった登場人物たちを苦しめるツールとして盛り込みたいと考えています。
LANDOER:本人が亡くなったあとも残り続けるSNS。そこにも不思議な感覚が残りますよね。
蓬莱:たしかに。亡くなったことによって、その人が書いていた言葉が正当化され、神格化されていくというのも、ある意味とても怖いことですよね。亡くなっている人のSNSが、生きている人間を糾弾していく——そんな歯車が、この作品を推進させていく気がしています。そして糾弾を食らった側は、それをどのように受け止め、どう進んでいくのか。本作はその答えを模索する物語になると思いますし、その糾弾に抗えるのか、闘い切れるのかまで描きたいと思っています。
LANDOER:吉高さんはSNSを使って多くの発信をされていますが、SNSというものをどのように感じられていますか?
吉高:SNSを利用していると、「発信するスタートラインって、みんなこんなにも一緒なんだな」と思います。私のような職業に限らず、どんな人でも発信が急にバズる可能性がある時代じゃないですか。それってまさに、アンディ・ウォーホルが言っていた“人は誰でも15分間だけ有名になる日が来る”という言葉そのもの。だからこそ、発言には気をつけなきゃいけないなと、日々意識しています。
LANDOER:言葉ひとつが誰に届くか予測できないからこそ、発信する以上、どの年代にも同じ意図が伝わる言葉でなければいけませんよね。特にいまは、子どもの頃からSNSがある時代ですし。
吉高:そうなんですよね。だから、大人の私たちよりもSNSの怖さを感じているのは、学生のみなさんなんじゃないかと思います。一度インターネット上に出てしまったものは、そこからずっと“寿命がない世界”で生き続ける。でも、学生の段階でその自覚をもって発言している人なんて、本当に少数だと思うんですよ。証拠として残り続ける過去…とても怖いですよね。とはいえ、私は夜な夜なSNSの縦型動画や見知らぬ人の配信ライブを観ています。会うこともない、得体も知れない人のライブを観て「同じ眠れない時間を過ごしている」と思うと、すごく不思議な気持ちになるんです(笑)。

Dear,LANDOER読者
パルコ・プロデュース2025
『シャイニングな女たち』
From 吉高由里子
ビュッフェを食べに行く公務員の現在と、フットサルをやる大学生、『金田海』が生きる二つの世界線を演じることになると思うのですが、どんな人にも、他人が知らない部分や人には言えない部分があると思うので、その多面性を表現できたらおもしろいかなと思っています。舞台上で本当にボールを蹴るのか、映像などの技術を使うのか——蓬莱さんがどんな舞台をつくられるのかも含めて、楽しみにしていてください。
From 蓬莱竜太
※「蓬」の正字は一点しんにょう
今回は、“スポ根少年マンガのような学生時代”と“大人になってからの現実”との乖離を描きたいと思い、フットサルチームのOGたちという設定にしました。青春の熱と現実の痛みが、エンターテインメントとして混ざり合うような作品にしたいと思っています。加えて、フットサルの動きを演劇でどう表現するかも、僕にとっては大きな挑戦。作品をつくるときには常に「どうすれば演劇のおもしろさを伝えられるか」を意識していて、本作ではフットサルと演劇、両者の魅力をどう交差させようかと考えているところです。いくつものギャップを描いて、観に来てくださるみなさんを楽しませたいと思っているので、ぜひ劇場に足を運んでいただけたら嬉しいです。



パルコ・プロデュース2025『シャイニングな女たち』
東京公演:PARCO劇場
2025年12月7日(日)~28日(日)
大阪公演:森ノ宮ピロティホール
2026年1月9日(金)~13日(火)
ほか、福岡、長野、愛知を巡回。詳細はHPにて。
作・演出:蓬莱竜太
出演:吉高由里子 さとうほなみ
桜井日奈子 小野寺ゆずる
羽瀬川なぎ 李そじん 名村辰 山口紗弥加
Staff Credit
カメラマン:興梠真穂
ヘアメイク:中野明海(吉高)
スタイリスト: 申谷弘美(吉高)
インタビュー・記事:満斗りょう
ページデザイン:Mo.et