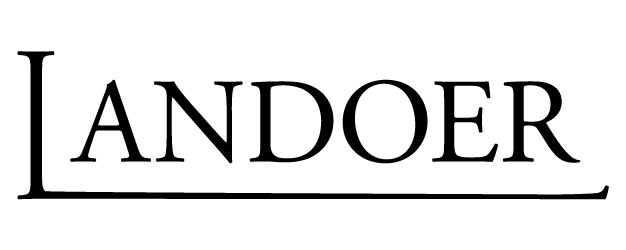映画『星と月は天の穴』
言葉の渦が私を巡る||
〝耳で観る一本〟の心地を
どうか贅沢に堪能して
人がもっとも自分を客観視できるのは、小説なり日記なり、〝生きた時間〟を文字に起こすときだと思う。そして、人がもっとも主観的で、倫理や道徳を忘れ本能に覆われるのは〈愛〉と〈性〉への耽溺の刹那だと思う。青々と春を楽しんでいた頃は、〈愛〉とは誰かから向けられ、〈性〉とは幸せの果てを感じるものだと思っていた。しかし、人生という名の小説が厚くなるにつれ、〈愛〉も〈性〉も、多大な自己生成と多少の脚色がなければ存在し続けられないことを知ってゆく。誰もが「できるだけ正統に咲いて欲しい」と願う、自分の〝精神の花〟。その根っこに潜むは、本能的な〝愛と性〟の血脈。この冬、ひとりの男の物語が、あなたの穴を埋めるかもしれない⸺
映画『星と月は天の穴』

荒井晴彦監督と
俳優 綾野 剛が織りなす日本映画の真髄
『ヴァイブレータ』(03)、『共喰い』(13)などキネマ旬報脚本賞に5度輝き、半世紀ものキャリアを誇る、日本を代表する脚本家・荒井晴彦。『火口のふたり』(19)をはじめ、自ら監督を務めた作品群では総じて人間の本能たる〝愛と性〟を描き、観る者の情動を掻き立ててきた。最新作『星と月は天の穴』は、長年の念願だった吉行淳之介による芸術選奨文部大臣受賞作品を映画化。過去の離婚経験から女を愛することを恐れる一方、愛されたい願望をこじらせる40代小説家の日常を、エロティシズムとペーソスを織り交ぜながら綴っている。主人公の矢添克二を演じるのは、荒井と『花腐し』(23)でもタッグを組んだ俳優 綾野 剛。着実にキャリアを重ね、名実ともに確固たる地位を築き上げてきた綾野が、これまでに見せたことのない枯れかけた男の色気を発露、過去のトラウマから、女を愛することを恐れながらも求めてしまう、心と体の矛盾に揺れる滑稽で切ないキャラクターを生み出した。そして、矢添を取り巻く女たち——大学生の紀子を演じるのは、新星 咲耶。女性を拒む矢添の心に無邪気に足を踏み入れる。矢添のなじみの娼婦・千枝子を演じるのは、荒井作品3作目の出演となる田中麗奈。綾野演じる矢添との駆け引きは絶妙、女優としての新境地を切り開く。さらには、柄本佑、岬あかり、MINAMO、 宮下順子らが脇を固め、本作ならではの世界観を創り上げている。1969年という日本の激動期を背景に一人の男の私的な物語を映す、滋味深き日本映画に、温故知新を感じることだろう。名匠 荒井晴彦の脚本から導き出された俳優 綾野 剛の真骨頂、映画界に一石を投じる<R18>の異色作が誕生した。
-STORY-
「あなたは軀と恋愛してるのよ」
妻に捨てられたこじらせ男の、滑稽で切ない愛の行方。
⼩説家の矢添克二(綾野 剛)は、妻に逃げられて以来 10 年、独⾝のまま 40 代を迎えていた。偶然に再会した大学時代の同級生(柄本佑)から、彼の娘が 21 歳になると聞いて時の流れを実感する一方、離婚によって空いた心の⽳を埋めるように娼婦・千枝⼦(⽥中麗奈)と時折り軀を交え、妻に捨てられた傷を引きずりながらやり過ごす日々を送っていた。実は彼が恋愛に尻込みするのには、もう⼀つ理由があった。それは誰にも知られたくない⾃⾝の〝秘密〟に、コンプレックスを抱えていることだった。不惑を過ぎても葛藤する矢添は、⾃⾝が執筆する⼩説の主⼈公・A(綾野=二役)に⾃分を投影し、20 歳も年下の大学生・B子(岬あかり)との恋模様を綴ることで、「精神的な愛の可能性」を探求していた。そんなある⽇、矢添は画廊で⼤学⽣の瀬川紀⼦(咲耶)と運命的に出会う。車で紀子を送り届ける途中、彼⼥の〝粗相〟をきっかけに奇妙な情事へと⾄ったことで、⽮添の⽇常と心情にも変化が現れ始めた。無意識なのか確信的なのか……距離を詰めてきては心に入り込んでくる紀子の振る舞いを、矢添は恐れるようになる。一方、久しぶりに会った千枝子から「若いサラリーマンと結婚する」と聞き、「最後に一緒に街へ出てみるか」と誘い、娼館の外で夜を過ごす。恋愛に対する憎悪と恐れとともに心の底では愛されたいという願望も抱く矢添は、再び一人の女と向き合うことができるのか……。
-矢添克二-

小説の中のA:
結婚生活に失敗した小説家・自身が書く小説の主人公
矢添克二
×
綾野剛
本作は矢添のバックボーンや行動、表情から感情までがすべてセリフに起こされていたので、“肉体化しない”ことを大切にしました。「ありがとう」というセリフがあったとして、活字だけ見ると『感謝』を意味する言葉だけれど、重なる表情によっては「本当に感謝しているのか」「やや怒っているのか」など、意味が変わることがある。このような場合は、人物設計を芝居や表情で補填していく必要があります。他にも「もう嫌だ」というセリフを、全身で動きながら「もう嫌だ!」と発するか、まったく身動きのない状態でそっと発するかなど⸺セリフの体幹部分を担うのは、おおよそ“肉体化”。ただ、今回の脚本には補填する部分がなかったので、荒井(荒井晴彦監督)さんの邪魔をしないために、あえて“肉体化”しないことを大切にしていました。自分は“セリフを読む拡声器”として存在することに徹する、と。

綾野さんという拡声器から聴こえてくる言葉たちが
とても美しく、重厚に感じました。
僕自身、脚本を読んだとき、言葉の渦にうっとりしました。詩・小説的で文学的⸺そんな脚本を生きるにあたって、自分の役割は“目で見せる映画”ではなく、“耳で観る映画”にすることにあると感じたんです。同時に女性たちが豊かな分、矢添が何もしないことがさらに良い効果を生むのではないか、と。結果、矢添がこじらせている男だということも表現できますし。この作品の脚本に対しては、それが一番正しい役者の在り方のような気がしました。役者というのは、作品の一血肉。本作はその役割を存分に活かしやすい作品でした。
言葉の渦にうっとり―…とてもよくわかります。
本作の舞台である昭和中期の言葉がもつ美しさ、
荒井監督の脚本に描かれている言葉の美しさは
綾野さんの心にどのように響きましたか?
時代性と言葉が非常にマッチングしていると思いました。言葉って、きっと本来はそうであるべきなのかもしれません。当時は、若年の僕らには聞き馴染みのない言葉を話している年配の方がたくさんいる時代でした。それってまさに、“言葉が(その人が生きた)時代を象徴している”ことの証明で。では、現代を象徴する言葉とは何を指すのか?⸺そんな時代において、本作はたとえ全編室内で撮影をしていたとしても、セリフだけで大体何年頃の話なのかが伝わります。すごい強みだな、と。衣装などは時代に合わせたものを着ていますが、その他の部分では、自分自身が1969年(本編の舞台となった年)に、特別何かを落とし込む必要がありませんでした。


まさに、荒井監督の脚本に書かれた
言葉の一つひとつにリスペクトがあるゆえの
“矢添作り”ですね。
唯一意識したことがあるとすれば、“声質を変える”ということでしょうか。昭和中期のニュースなどを観ていると、皆さん出力が強く張りがあり、声が甲高い印象を受けるのですが、それは当時のマイクの性能の問題もあり、音声のハイの部分だけを拾って、ローの部分を拾っていなかっただけなんじゃないかと思っていて。となると、僕たちは実際のその人の声を知らないということになる。スクリーンに映る矢添の声も、本当の声は知りえないということになれば、多くの情報が遮断されてセリフだけに集中できるようになる。そう思い、“肉体化”を防ぐためにも、なるべく情感をもたせず“昔のラジオ”のような声を意識してセリフを発していました。
個人的に、柄本佑さんとのシーンでの
情感がないながらも、テンポ感が非常にいい
言葉の往来がとても好きでした。
ピストルのようなやりとりですからね(笑)。僕は柄本佑フリークでもあるので、彼の弾を受けて心地よくなっていると、あっという間に置いていかれてしまうんです。そのくらいテンポが軽快なんです。だからといって、決して反射で返しているというわけでもありません。あれは本当に、彼の芝居の上手さゆえに成立しているやりとりだと思います。(LANDOER「たしかに。観ていても、矢添のセリフに対する返答に一考があるように感じます。」)そうなんです。前回の『花腐し』に続き、彼はある種“声に情感を込めない”発し方をしているような気がします。とてつもなく抑制されたなかで、出力だけパンッと弾くような。彼と矢添の橋でのシーンは撮影初日に撮ったものなのですが、僕としては初日からとんでもない弾を受けさせていただき、ほくほくした気持ちで帰ることができました。

お話にも出てきた、前作『花腐し』。
撮影時、荒井監督は
「綾野さんは役を細かく考えてきてくれた」と
仰っていましたが、
本作では監督とどのようなお話をされましたか?
今回、僕からお話ししたのは“声質を変える”ことくらいだったと思います。即興の芝居や中途半端な頷きも一切なく、本当にきっちり台本通りに演じました。とにかく「荒井さんが書かれた脚本の文体の美しさが、そのまま伝わってほしい」と思いながら。美しくて、滑稽で、少し変。それらの要素をそのまま伝えるためには、僕が余計な情感を入れてはいけないと思ったんです。『花腐し』は現代劇だったこともあり、ある程度ムードを作っていく必要があったのですが、今回は、あるとすれば咲耶さん演じる紀子や、田中麗奈さん演じる千枝子と対峙する際の言葉の紡ぎ方の変化、ということくらいでした。そこに関しては、矢添の〈人間味〉という部分で必要だと感じたのだと思います。

女性たちの存在が、
矢添の〈人間味〉の起点でもあったのですね。
先ほども「女性たちには豊かでいてほしかった」と
仰っていましたが、
本作に登場する女性たちの姿は、
綾野さんに目にどう映っていましたか?
紀子も千枝子も、岬(岬あかり)さんが演じられたB子も、お三方ともシンプルに格好いいですよね。それぞれに表現が違っていて、なかでも咲耶さんは“あの時代を生きているマインドがすごく強い”と感じていました。セリフの発し方も、どちらかというと矢添に近い話し方で、もともと当時の音楽や映画に対して造詣が深い方でしたので、とても心地よかったです。一方で田中麗奈さんは、“感じたことをそのまま、自分のスタイルをもって伝えてこられる方”。それは、積み重ねられた〈年輪〉が紡ぐお芝居だなと思います。何度か共演させていただいているのですが、いつもハッとさせられ、学びしかありません。そして岬さんは、本作の女性陣のなかで一番現代的にナチュラルにお芝居をされていて、対峙しながら“時代に引っ張られていない表現”を感じていました。矢添が書く小説の登場人物・大学生B子という設定において、その在り方がものすごく効果的で。1969年という時代のなかで「自分にできることは何か」を考えられたうえで、自然なお芝居を選択できるというマインドが素敵です。芝居を観ることが好きな自分としては、皆さんの表現を浴びることができるとても贅沢な時間でした。

こじらせている矢添と、
まっすぐに向き合ってくる女性陣。
いまの時代の男女関係にも
リンクしているものを感じました。
個人的に、男性は生命体としても“生かされている”ように思うので。人はみな女性から生まれてくる。だからこそ男性は、女性に対してある種の〈畏怖〉をもっているように思うんです。ただこの映画は、単純な〈畏怖〉の感情だけでなく、女性への“敬意”や“リスペクト”など、すべて含めたものをとても大切に描いている作品だと感じています。映画の舞台は1969年ですが、現代の方々に楽しんでいただく作品である以上、いまの時代のリテラシーもとても大切。そのうえで本作では、咲耶さんが当時の空気感や奥行きを纏いながら、物語を支える肉体的な表現を担われていて。ほぼ初めての主役といっても過言ではない立場で紀子を演じておられたので、「映画って楽しいな」「役者の仕事を続けていきたいな」と思っていただくところまでが、我々の仕事だと思っていました。いい形で一緒に作品作り・役作りを行っていくのはもちろん、おこがましくも、お芝居の楽しさや個人を超えて集団で何かをつくることの豊かさを届けられたらいいな、と。最後に咲耶さんから「すごく楽しかったです」という言葉をいただくことができて、とても嬉しかったです。

Dear LANDOER読者
映画『星と月は天の穴』
From 綾野剛
様々な映像に溢れているいま、本作は決して作りやすいタイプの作品ではないと思っています。それでもこうして完成できたのは、この作品を制作するにあたって、いろいろな方が旗を上げて協力してくださったから。自分もその一編に関わることができてとても幸せです。同時に、いろいろなジャンル・規模感の作品を行き来し、映画に救われてきた身としては「自分が関わることで、一人でも多くの方にこの作品を観ていただけるチャンスが広がるのであれば、身を投じたい」という気持ちで参加させていただきました。映画をご覧いただく方も、小説を読みたいと思っている方も、ぜひ『星と月は天の穴』を楽しんでください。

映画『星と月は天の穴』
2025年12月19日(金)公開
出演:綾野剛
咲耶 岬あかり 吉岡睦雄 MINAMO
原一男 / 柄本佑 / 宮下順子 田中麗奈
脚本・監督:荒井晴彦
原作:吉行淳之介「星と月は天の穴」(講談社文芸文庫)
制作・配給:ハピネットファントム・スタジオ

Staff Credit
カメラマン:興梠真穂
ヘアメイク:石邑麻由
スタイリスト:佐々木悠介
インタビュー・記事:満斗りょう
ページデザイン:Mo.et